|

[ 単行本 ]
|
「特攻」と遺族の戦後
・宮本 雅史
【角川書店】
発売日: 2005-03
参考価格: 1,680 円(税込み)
販売価格: 1,680 円(税込)
中古価格: 580円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・宮本 雅史
|
カスタマー平均評価:  5 5
 涙・涙・涙の感動作でした・・・ 涙・涙・涙の感動作でした・・・
特攻隊員と残された家族に焦点をあて、その波乱の人生と苦悩と悲しみが綴られた一書です。妻を持つ青年士官から、まだあどけなさの残る十代の少年航空兵まで陸軍振武隊4名のエピソードがあり、著者の随筆で締めくくる。
どれを読んでも共通して感じるのは、隊員と遺族の崇高なまでの澄み切った心ですね。隊員の家族に宛てた手紙なども多数掲載されておりますが、およそ16や17歳の少年の文章とは思えぬ自立した物言いに愕然とします。軍国主義の教育体制とはいえ、自己を律し、倫理を重んじる精神、芯の強さや愛国心は現代の日本人では到底到達できない高き所にある。人間として一段も二段も上であったのは間違いないところでしょう。
特攻に関する出版物は相当な数にのぼりますが、本書は隊員もさることながら、残された遺族に多くの比重を持たせている点が特徴といえます。私は通勤電車を読書時間に当てているのですが、涙が溢れそうになる場面が何度もあり、困ってしまいました。是非ともおすすめしたい一書です。
|
|

[ 単行本 ]
|
ユキは十七歳 特攻で死んだ―子犬よさらば、愛しきいのち
・毛利 恒之
【ポプラ社】
発売日: 2004-09
参考価格: 1,365 円(税込み)
販売価格: 1,365 円(税込)
中古価格: 689円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・毛利 恒之
|
カスタマー平均評価:  5 5
 日本人の死に様 日本人の死に様
この書は、特別攻撃隊・第七十二振武隊の五名の若者の最後に焦点を合わせて、記されている。この五名の享年は、十八歳若しくは十七歳である。誠に御立派な死に様であった。与えられた大命に殉ずるその大和魂を日本人は忘れてはならない。先の戦争で、祖国のために命を御捧げになられた全ての英霊に対して、一切のイデオロギーを捨てて、感謝と忠義を尽くそうではないか。日本人特有の徹底した精神主義で、米国を呑み込んでしまおうではないか。尚、「パール判事の日本無罪論」を併読されることを強くお薦めする。
 17歳の特攻飛行兵のありのままの姿 17歳の特攻飛行兵のありのままの姿
この本で初めてライトを当てられた荒木幸雄さんの生き様を貴重な資料で書き綴られている。
この本の中の一節に、「彼の生まれた年、日本は日中戦争をはじめ、富国強兵を詠い、軍国主義という教育を与え、17歳に成長した彼に今度は特攻で国のために死ねという」と言うようなことが書いてありました。
歴史というのはその時その時、皆それがベストな事と思い込んでいる場合が多いように思うが、本当に悲しいことはそれがその時代、当然のようになっていたこと。
特に、人為的な「戦争」という悪質な状況下で、精一杯愛する人を守ろうとして特攻という任務を決行した彼らの生き様を、まして、最少年17歳の特攻飛行兵の彼の生き様を少しでも多くの人に知ってもらいたいと思う。
|
|
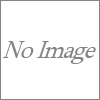
[ 単行本 ]
|
インディアンに囚われた白人女性の物語 (刀水歴史全書)
・メアリー ローランソン ・ジェームズ・E. シーヴァー
【刀水書房】
発売日: 1996-08
参考価格: 2,940 円(税込み)
販売価格: 2,940 円(税込)
中古価格: 318円〜
( 通常3〜5週間以内に発送 )


|
・メアリー ローランソン
・ジェームズ・E. シーヴァー
|
カスタマー平均評価:  4 4
 北米史のもう一つの断面 北米史のもう一つの断面
なにやら意味ありげな感がないでもない題名だが、貴重な内容である。原住民に捕虜になった白人女性の回想がつづられている。
はっきりと分かるのは、インディアン=獰猛な野蛮人、ではないという、当たり前と言えば当たり前の事だ。
あくまで白人側から見た記述なので、白人至上主義的な大前提での物言いも見られるが、開拓期の北米大陸の実際状況の過不足ないリアリティへの手がかりを得るのに良い貴重な資料である。
|
|
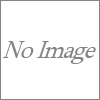
[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
過去の克服・二つの戦後
・R.V. ヴァイツゼッカー ・山本 務
【日本放送出版協会】
発売日: 1994-08
参考価格: 968 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 4,452円〜

|
・R.V. ヴァイツゼッカー
・山本 務
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
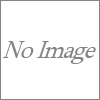
[ 単行本 ]
|
パンツァー・フォー
・カール アルマン
【大日本絵画】
発売日: 1988-03
参考価格: 3,045 円(税込み)
販売価格: 3,045 円(税込)
中古価格: 600円〜
( 通常4〜5日以内に発送 )


|
・カール アルマン
|
カスタマー平均評価:  5 5
 ドラマチックな戦車兵のエピソード ドラマチックな戦車兵のエピソード
東西戦線から北アフリカまで広大な戦線で戦った15名のドイツ軍戦車兵の個人戦記。
あまりに広大な戦線の中からのエピソードなので、ある程度、戦史の知識が必要ですが、
開戦から終戦まで戦い抜いた者、命を落とした者、途中で捕虜になった者とどれもがドラマチックに描かれています。有名どころはバルクマンやカリウスのエピソードですが、個人的にはナイグルのエピソードがオススメです。
これは4人の兄をスターリングラードや爆撃で無くした母が最後の末息子だけはそばにいさせて欲しいと言う願いを軍が聞き入れ、
ナイグルは除隊し帰国するが途中でソ連軍の包囲に巻き込まれる…。
そう!あの映画の様なストーリーなんです。
|
|
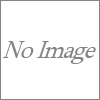
[ 文庫 ]
|
陸軍特別攻撃隊〈第2巻〉
・高木 俊朗
【文藝春秋】
発売日: 1986-08
参考価格: 567 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 800円〜

|
・高木 俊朗
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
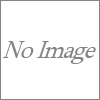
[ 文庫 ]
|
陸軍特別攻撃隊〈第1巻〉
・高木 俊朗
【文藝春秋】
発売日: 1986-08
参考価格: 567 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 400円〜

|
・高木 俊朗
|
カスタマー平均評価:  5 5
 高木俊朗作品では一押しです 高木俊朗作品では一押しです
高木俊朗作品では最もお勧め。マイナーな陸軍特別攻撃隊の実情を知ることができる。この中に出てくる、隊員たちは戦争狂いなんかではなく家族を愛し精一杯生きた人たちばかりで、こんな人たちを死なせてしまった戦争がとても愚かなことに感じられる。その隊員たちに命令していた上官たちは偉そうに命令するばかりで、戦争が終わったらしゃーしゃーと生き延びてしまう。何か失敗が有っても誰も責任を取らない今の日本社会はこのころとまったく変わっていないということを感じてしまう。その中で一人の隊員が自らの主張を貫き特攻死せず生き延びて帰還するの救い。ほかの高木作品も当然お勧めです。文字数が足りん。
|
|

[ 単行本 ]
|
ザ・メイン・エネミー〈上〉 -CIA対KGB最後の死闘-
・ミルト・ベアデン ・ジェームス・ライゼン
【ランダムハウス講談社】
発売日: 2003-12-12
参考価格: 1,995 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 332円〜

|
・ミルト・ベアデン
・ジェームス・ライゼン
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本 ]
|
西欧の植民地喪失と日本―オランダ領東インドの消滅と日本軍抑留所
・ルディ カウスブルック
【草思社】
発売日: 1998-09
参考価格: 2,310 円(税込み)
販売価格: 2,310 円(税込)
中古価格: 1,740円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・ルディ カウスブルック
|
カスタマー平均評価:  5 5
 東インドのオランダ人 東インドのオランダ人
オランダには強烈に日本を憎む老人達がいる。かつての東インドのオランダ人。
彼らは植民地のインドネシア人を奴隷のように扱い、王侯貴族のように君臨していた。
アジア人種は欧米人種より劣るという(彼らの)理由から、それを自然として享受していた。
そこへ日本軍がやってくる。「アジアはアジア人のものだ」という当面の(半分は本気の)
大儀をかかえて。
たった8日間で東インドのオランダ帝国は崩壊する。
白人至上主義が非西欧の曲がり足の黄色い猿(日本人)に崩される。オランダ人を捕虜抑留所に入れた日本兵は、残虐行為も行う。 ちょっとでも(西欧人が)抵抗の気配をみせたり、”場違いな西洋人の優越感”を示そうものなら、
即刻、(日本兵は)わが使命とばかりに殴りつける。 むきになって制裁を加えた日本兵。白人の優越感、しいては黄色人の劣等感は、
彼らのもっとも嫌うところであったことは現代人には理解しやすい。
著者は人種差別がない人間で、日本兵がオランダ捕虜にやった残虐行為を、インドネシア人を奴隷
扱いしていたオランダ人が責めることは出来ないと言う。 残された日本兵の日記には、暴力の渦中(暴力行為をし、戦局が逆転すれば受けもする立場)
にいて、その暴力の下らなさを諦観する内容が目立つ。
東インドのオランダ人は、優勢人種の権利(暴力)を取られたことに苛立ち、
日本側は、暴力によって自分の人種的劣等感を打ち砕こうとする。 優勢側が暴力をふるう、劣勢側が暴力をふるわれるという戦争定理。
白人至上主義 対 人種劣等感打破、
生を謳歌したい西欧人 対 死か国家の勝利しかなかった日本人 また戦後に書かれた著書が、どれだけ著者の解釈、「決まり文句」にゆがめられ、
実質的体験からかけ離れたものであることを警告する内容。良書です。
 「朝日新聞」の姿勢 「朝日新聞」の姿勢
日本軍がアジア諸国を侵略したといった類の「反省」は日本のメディアに頻繁に現れるのに、英国やオランダが行ったことはほとんど問題にされない。そしてひたすら、英国人やオランダ人が、太平洋戦争中、日本軍の捕虜になって苦しんだといった記述ばかりが現れる。その最たる場が「朝日新聞」である。
しかしオランダ人であり、抑留経験もあるカウスブルックは、多くのオランダ人が、日本の侵攻によって結果的に東インド(インドネシア)を独立させられたことに怨みを抱き、黄色人種でありながら白人に逆らうなどというのは生意気だと思っている、と指弾する。しかしこれほど重要な本を「朝日」は書評に取り上げようとせず、アジアのみならず英国やオランダに対してさえ、ひたすら、日本の「反省・謝罪」が足りないと言い募るのだから、「自虐」と呼ばれても仕方あるまい。ようやく、日英同盟百年を期に、木畑洋一氏による英国の帝国主義への批判が載ったのが救いである。戦勝国の行為も指弾されなければならないという当然の立場に「朝日」が立ち返ることを期待したい。
 風車とチューリップと植民地 風車とチューリップと植民地
「赤道にかかるエメラルドの首飾り」と称されたインドネシアがあの「小国」オランダが大国になる富をもたらした、とも言われています。そのオランダが戦時中の日本の行動(このこと自体いろいろ論議されていますが)に対して口を開く時に、では己がインドネシアに対して行ったことは棚にあげて・・・?とsilent majority は思うのです。そんな疑問に答えてくれる一冊がこの本です。私自身はオランダが大好きです。チューリップ、チーズ、風車、木靴、節約家・・・以上にオランダに関して勉強してきましたし、オランダ語も学習してきました。だからこそ、よけいにこの類の難しい問題からも目をそらさず、きっちりと勉強して物事の本質を理解していく必要があると思いました。出版されてすぐに買い求め一気に読みました。難しい事柄に対する答えもたくさん見つかりました。と同時にオランダに対する理解が深まりオランダという国が(安心して?)ますます好きになりました。好きだからこそ勇気をだして読まなければならない書だと思います。
|
|

[ 文庫 ]
|
敵対水域―ソ連原潜浮上せず (文春文庫)
・ピーター ハクソーゼン ・R.アラン ホワイト ・イーゴリ クルジン
【文藝春秋】
発売日: 2000-10
参考価格: 700 円(税込み)
販売価格: 700 円(税込)
中古価格: 1円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・ピーター ハクソーゼン
・R.アラン ホワイト
・イーゴリ クルジン
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 ドキュメントのようなサスペンス、サスペンスのようなドキュメント ドキュメントのようなサスペンス、サスペンスのようなドキュメント
現場の潜水艦乗りと米ソの政治家の動きがつぶさに見えるリアリティがすごい。小説ではあるものの、当事者に綿密にインタービューを行って書かれているので、ソ連ミサイル原潜K-219の事故前後に関するドキュメンタリーのように読めます。それでいて手に汗握るサスペンスとしても大いに楽しめる。翻訳の質が素晴らしい。
 『人間も捨てたもんじゃない』と認識せてくれる一冊 『人間も捨てたもんじゃない』と認識せてくれる一冊
1986年、バミューダ沖で火災事故を起こして沈没したソ連ミサイル原潜K−219のドキュメント。アメリカの新鋭原潜に比べると故障だらけのおもちゃのような潜水艦で立ち向かうK-219の乗組員。沈没、有毒ガスの充満、原子炉の暴走、と次々に危機に見舞われていく中で部下や仲間を救う為に自らの命を当然のごとく捧げる乗組員の姿には人間の美しい部分を見せられた気がします。特に原子炉の暴走を食い止める為に、火災の中を制御棒を手動で下ろしに単身制御室へ乗り込んだプレミーニンが仲間の元に戻る寸前で力尽きる箇所は何度読んでも涙なしには読めません。 自分の保身の事ばかりを考えるソ連首脳部や原潜の事故という状況の中で乗組員達の自己犠牲の物語が進行しているというのは何とも皮肉な気がしますが、『人間も捨てたもんじゃない』と認識させてくれる一冊です。
 ココム違反事件の背景が。 ココム違反事件の背景が。
1980年代初頭に東芝機械の9軸竪型旋盤が当時のソ連に2軸の旋盤と偽って輸出され、原潜スクリューの加工に活用され、消音の成果が著しいものだった。この事件のK219は1970年代の旧型原潜で騒々しくアメリカの探知も容易なものだったことが分かるが、事件の中でもソ連の最新鋭原潜ヴィクター級はアメリカのオーガスタの探知をうまくかいくぐれるレベルにまで達している。この事件を契機に東芝機械のココム違反が表面化、日本にとっての大事件に発展することになる(当然アメリカも知っていて、それまでは泳がせていただけなのだろうが・・。この事件で犯人を作り責任を転嫁しなければならなかったからだろう)。
まあ、そんなことは番外編で、本は緊迫感に満ちた一気に読ませるドキュメンタリーノベルとして水準が非常に高い。翻訳が優れていると感じる。
 原潜の真実を知った本 原潜の真実を知った本
去年のクルスクの沈没。また練習船との衝突事件。原潜というものがいろんな形で家庭に入りこんでいる今日。この本はお勧めです。この本は小説という形態はとっていますが、当事者にインタービューを行い、1986年の事件を米ソ両方の立場でみることができます。艦長の勇気ある行動には脱帽しました。人が主役の真実としてお勧めします。
 読み終わるのが惜しいほどの面白さ 読み終わるのが惜しいほどの面白さ
どの程度真実に近いのか測りかねるけれど、申し分のないリアリティと迫力である。潜水艦内部のメカニック、乗組員の心理、米ソ双方の権力の在り様と駆け引き、等々読者の興味をひく要素は盛沢山で、まずは飽きることがない。私が最も興味をひかれたのは、米ソ権力の生態であった。それらの作用反作用はいかにも複雑な動きを見せるけれども、枝葉末節を取っぱらってしまえば、いかにして相手より優位に立つかということであり、これは要するに悪ガキの頭争い、縄張り争いとなんら変わるところがない。さらに突き詰めて言えば、自然界における動物達のそれと同じである。と言うことは 人間はいかにも進歩しているようだけれど、実はそれはとんでもない迷妄で、国家間の交渉、あるいは権力内部の闘争における!原初的な駆け引きを見れば、いかにも頭脳プレイのようでありながら、本質は、本能に駆られての右往左往ではないのか、という至極幼稚な結論にたどり着くことになる。だとすれば、高邁な平和主義なんぞを持ち出す事は、かえって事態を紛糾させて剣呑ではないのか。 しかし、本書はそんな屁理屈なんぞなんのその、サスペンスとしても一級品である。また訳文が秀逸であることもありがたい。
|
|



