|
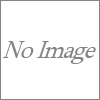
[ 文庫 ]
|
零戦撃墜王―空戦八年の記録 (光人社NF文庫)
・岩本 徹三
【光人社】
発売日: 1994-05
参考価格: 840 円(税込み)
販売価格: 840 円(税込)
中古価格: 365円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・岩本 徹三
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 戦神に愛された男 戦神に愛された男
日本海軍トップの撃墜王。
彼の淡々とした戦史の中に。
戦いが日常化している現実を見、
また、男の闘争本能をみる。
理不尽な軍隊の中で、
精一杯自分に与えられた任務を果たした、
下士官の記録。
彼の記録した撃墜数202機は、
男の矜持である。
これを信じなくて、なにを信じようか。
日本の搭乗員は大変優秀だった。
あの長い戦争の中で、
前線に立ちながら、生き残ったいた
撃墜数202機は、太平洋戦争一である。
あの長い戦争を
撃墜王として生き残った。
それだけでも、素晴らしい。
戦神に最も愛された零戦搭乗員である。
光人社編集がちょっとなぁと感じているので、
星は4つ。
現在入手困難だが、
零戦撃墜王―空戦八年の回顧
こちらなら星5つ。
天下の浪人虎徹。
彼は自らを浪人と評している。
日本の海軍の中で、
自分を浪人と感じていた彼が。
哀しくて愛しい。
 撃墜数202機に偽りなし!! 撃墜数202機に偽りなし!!
中国、真珠湾、アーリューシャン、ラバウル、トラック、フィリピン、沖縄。
岩本は常に戦場にいた。
撃墜数が多いのはその多くが邀撃戦によるものだからだ。物量の敵は100機200機と一日に何回も爆撃に来る。
敵の数だけ撃墜数も増えていく。
坂井三郎の大空のサムライと違うコースを歩んでいるのも読む価値のあるところだ。
坂井が開戦時台南空からフィリピンを攻撃したのに対し、岩本は真珠湾、珊瑚海海線と空母搭乗員だった。
坂井はガダルカナルでの出撃で負傷し日本へ帰国したのに対し、岩本は日本が苦しいときも常に第一線で戦い続けていた。
18年にはすでにこう言っている。
「もう誰の目にも勝敗は明らかだった。我々はただ卑怯者になりたくないために戦っていた。それがラバウル魂だ。」
沖縄戦ではさよならバンクをふって敵艦に体当たりする特攻隊を見送るシーンが何度となく描かれている。どんな気持ちで見送っていたのだろう。
 零戦撃墜王 空戦八年の記録 零戦撃墜王 空戦八年の記録
冷静沈着にして勇猛果敢 優れた状況判断 毎日が生死をかけた 空中戦の日々を淡々と書いておられるが 現在の私達が生きている生活環境
では想像もつかない日々を生き抜いてこられたことは嬉しい限りです
戦後は戦中とは違う戦いの日々だったと思いますが若くして亡くなられた事は残念です 岩本氏の生の話や記事などをもっと見聞したかった
 岩本ファン必読 岩本ファン必読
岩本氏の戦闘記録を読んで、興味深いのは次の2点である。第一に、戦術眼で勝敗が決まるということ。敵がどの位置からあらわれるか、どんな機種があらわれるか、どこまで深追いしてよいか、ということを、岩本氏は、おそらく天才と経験で知っていたのである。
この本には書いてないが、岩本氏の視力は1・0くらいだったといわれる。しかし、敵機の発見は早かったというのは、読んでいたからなのだ。同様のことは、坂井三郎氏も指摘している。 第二に、集団行動では指揮官の能力で全員の運命がきまること。経験の浅い指揮官に率いられた部隊は全滅に近くやられ、逆にすぐれた戦術眼をもった指揮官が率いると、味方の損害は少なく、戦果が上がる。
このあたりは現代の組織にも通じるものがあるだろう。
とくに戦争では、人の生死という形で、はっきりそれがあらわれるので、おそろしい。 文体の変化が興味深い。中国戦線では、高度をさげて牧場の牛をおどかしたりして遊んでいたし、珊瑚海海戦でも、張り詰めた中にも武人として充実していたことが伺われる。
ガラっとかわるのが、珊瑚海海戦の帰投からである。珊瑚海海戦で、岩本氏は、初めて一作戦で味方が多く失われるのを経験し落胆する。そして内地にもどってミッドウェイの敗戦を知る。
そこからは、読んでいても、いらいらしているのがよく伝わってくる。
開戦初頭のような充実感は影をひそめ、せまりくる敵にとにもかくにも立ち向かっている、という印象である。
要するに、珊瑚海、ミッドウェイあたりを境に、岩本氏の意識から、戦争への勝利、という目標が消えていくのである。
ラバウル防空戦も本書のハイライトのひとつだが、それとても、勝利への一歩というつもりで戦っていたのではない。壁がくずれないように支えている、という印象を持つ。
仕事をする人間として、こういう状況はつらいものがあっただろう。 特攻についても、短いが印象的な記述がある。特攻が知れ渡ると全軍の士気は目に見えて落ちた、というものである。
岩本氏のような歴戦のパイロットになると、精神論はともかく、戦術としての特攻攻撃の無意味さを、当時の前線の状況から、しみじみと悟っていたのであろう。
 日本海軍航空隊の至宝 日本海軍航空隊の至宝
撃墜機数202機!伝説のトップエース、日本海軍航空隊の至宝が書き遺した撃墜記録。日本最高の撃墜記録を持つ、岩本徹三 元海軍中尉(34期操練)の豊富な実戦経験、撃墜の真髄を書き記した回想録。
本作品は岩本氏が公表するつもりで書かれた回想録であったが、
昭和30年に病死されて以来、ご婦人のもとに保管され、日の目を見る事のなかった彼の遺稿である。まさに海軍いや日本の至宝であった岩本氏の遺稿を読まずして、空戦は語れないでしょう。
どちらかというと欧米型である一撃離脱戦法を極意とする。
巴戦(旋回し合って背後を取りあう戦い)は最終手段とするのが、撃墜王に共通する戦い方といえよう。しかも彼は、操練出身の兵隊あがりにも関わらず、中隊長を務めていたのである。搭乗員が不足していたとはいえ、彼に対する軍のよせる期待の大きさが伺える。まさに特別待遇と言える。
また、三号爆弾(空対空爆裂弾)の第一人者である岩本氏の投弾方法なども書かれており、非常に興味深い。彼の文章は自信に満ち溢れ、空戦を極めた男のかもしだす一匹狼的な雰囲気が感じられる。
また愛機に描く「桜」の撃墜マーク(大型機は八重桜)に誇りを持っておられたようで、文中にもしばしば登場する。しかも桜が60個以上ついた歴戦の愛機は、内地に送られて国民を鼓舞する為に展示されたのだそうだ。後輩たちも、その無数にある撃墜マークに憧れ、畏怖したであろうことは想像に難くない。敵機も253-102号機には一目置いていたに違いない。常に最前線にあって、終戦まで活躍した数少ない英雄の遺稿を是非読んで欲しい。
|
|

[ 文庫 ]
|
私は魔境に生きた―終戦も知らずニューギニアの山奥で原始生活十年 (光人社NF文庫)
・島田 覚夫
【光人社】
発売日: 2007-09
参考価格: 1,000 円(税込み)
販売価格: 1,000 円(税込)
中古価格: 798円〜

|
・島田 覚夫
|
カスタマー平均評価:  5 5
 寝不足になった・・。 寝不足になった・・。
就寝前に本を読むのだが、寝不足になった。
このような複数人による長期原始生活の話は、今後出てこないだろう。
モンゴロイドとしての環境順応性ではなく、日本人独特のものがあるのではないかと強く感じた。戦後60年、平和の下で疲弊した日本人に活力を与えてくれる本です。映像としても見てみたいと思った。
 面白すぎるサバイバルの実録本 面白すぎるサバイバルの実録本
どんな冒険家も体験し得なかったほどのすごい冒険。そして、並の小説家よりも達筆で読みやすい文章。大作ですが一気に読み切ってしまいました。 敵から隠れての籠城、食料の採取、戦友の死、農園の開墾、原住民との交流、すべてがスリリングで面白く、そして悲しくて涙が出ます。
アウトドア、戦争、原始時代、愛国心・・といったキーワードにピンと来る方すべてに、絶対にお薦めの本です。
 こんなに凄い本があったのか! こんなに凄い本があったのか!
この本は皆さんに絶対読んでほしい一冊です。
南海の島ニューギニアで敗戦を知らずに10年もの間、原住民も近寄らぬ山奥で原始生活を送り、生還した陸軍兵士たちの回想録です。
このような体験をされた方の手記は非常に貴重な文献だと思う。
今後もこれほどの体験が記された本を読める機会はそうそう無いかと思います。昭和30年に帰還して執筆を開始され、完成した昭和31年夏から、なんと30年もの間、刊行されず埋もれていたのだそうです。著者自身も半ばあきらめていたが、同じ部隊出身の先輩方の御尽力で昭和61年8月、ついに出版できたのだそうです、これにはまったく感謝ですね。
しかしこんなに凄い本があったのか!と感動してしまいました。
ニューギニアに上陸した米軍から逃れる為、退却に移る日本軍。
手持ちの食料もほとんどなく、敵に包囲された彼らは相談の末、山奥へ籠城し、自給生活を送る事に決する。友軍の巻き返しを信じて・・・。 560頁余の大書ですが、退却路を断たれて籠城を決意するまでの序章のみが軍隊としての行動であり、残りのほとんど全てが原始生活の記録である。その後10年もの長期に渡り、自給生活に入る。当初17人した同胞は敵の襲撃やマラリアなどで次々に倒れていくのが悲しい。
敵軍と交流のある原住民からも姿を隠して社会から完全に隔絶された世界で生きてゆく事の辛さが、ひしひしと伝わってくる。 生きていく為の最も重要な問題は「食べる事」。当初は敵の食料集積地に忍び込んでまかなっていたが、それも間もなく尽きてしまう。そこで彼らは、何もないジャングルを開墾し、農園を開いた。これは、気の遠くなる作業であり、並みの人間では実現不可能であったのでは無いかと思う。火を起こす道具も無い、武器も無い、しまいには衣服にも事欠くありさま。あるのは、「生」に執着する人間の底力だけ。
誰も体験する事の出来ない世界ですね。椎名誠氏が絶賛するのも納得です。圧巻なのは、数年後にとうとう原住民に発見され、接触を受ける場面。読んでいて緊張しました・・・。しかし誠実な態度で交渉し、ついに彼らとの交流が始まる。
相手の言語(コーヤ語)を覚え、お互いが信頼し、強い絆で結ばれるまでに交流を深めているところが凄い。おそらく今でも彼ら4人の存在は、原住民の間で語り継がれている事だろう。オランダ官憲に発見され、収容される事となるが、農園を離れる際に彼らは椰子の木を20本植えている。これは実が熟れるまで30年近くかかるのだそうで、原住民が収穫する時、自分達の存在を思い出して欲しいとの願いが込められている。今頃は立派に実を付けて、彼ら日本兵の恩恵であると、収穫する原住民の語り草になっているのだろうなぁ。この本は読まないと本当に後悔する一冊ですよ!!
|
|

[ 単行本 ]
|
時代を動かした闇の怪物たち 昭和・平成 日本「黒幕」列伝 (別冊宝島)
【宝島社】
発売日: 2005-05-27
参考価格: 840 円(税込み)
販売価格: 840 円(税込)
中古価格: 198円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
|
カスタマー平均評価:  3 3
 興味の幅が増えました 興味の幅が増えました
日本の歴史を学ぶには外せない人たちですね。
何が真実かなんてわからないけれど、彼らに対して共感する部分がなければ、成功者にはなれないんだろうなと思います。
児玉誉士夫、小佐野賢治、笹川良一等それぞれを著した本を今後読んでいきたいと思いました。
まずは、田中角栄に関する本でも読んでみようと思います。
 抗し難き負の魅力 抗し難き負の魅力
人間は本質的に善なのか?悪なのか?正義のヒーローにあこがれる反面、悪党にも心を奪われる時がある。そう、ヒトラーを信奉するものが未だに後を絶たないように。
「黒幕」−表に出ないというそれだけで負の香りが漂う彼らの経歴を紹介したものが本書です。児玉誉士夫、笹川良一といった超大物フィクサーから、許永中、浅田満といった比較的最近の人物まで幅広く網羅しており、それだけでも価値があります。惜しむらくはムックという装丁のため紙幅が足らず、個々人の紹介が寸足らず気味だということです。本書は入門書だと割り切り、後は興味を持った人物を個別に当たるというやり方がベストでしょう。
それにしても本書に納められた黒幕たちの経歴を見ると、貧しさの中苦学して身を起こしたり、差別をバネにして飛躍したり、思想的にはあくまでも純粋だったりと、読んでいてふと人間的魅力を感じてしまいそうになる瞬間があります。なぜ、彼らは闇の世界の住人となってしまったのか、我々も一歩踏み外しただけで「そちら側」へといってしまうのではないか、そもそも「表の世界」と彼らとの差は何か、そういったものに思いを巡らしてしまうのです。
 もっと分厚くして欲しい。 もっと分厚くして欲しい。
なかなかおもしろい。
最近までは絶対書けなかった浅田満などに触れていて興味深い。
読んでいると叶美香とか細木数子、デビ夫人、美空ひばりがいかにおっかない世界に身を置いているかがわかる。笹川良一にも触れているのだがさてさて糸山先生は今後のJALをどうお考えなのやらとかそんなことを考えながら読むとおもしろい。
明らかに糸山先生の話題をこの章は外した気がする。 21世紀を迎えて新たなるタブーの解禁に挑戦しているように思えた。 おもしろい。
おもしろい。
おもしろい。 もっと分厚くして欲しい。 総合的な評価は右翼プロレス名鑑に最新版てとこだろう。 おもしろいのは新しい話題を扱っているという点であり、従来のネタに関しては特に工夫はない。
 もっと分厚くして欲しい。 もっと分厚くして欲しい。
なかなかおもしろい。
最近までは絶対書けなかった浅田満などに触れていて興味深い。
読んでいると叶美香とか細木数子、デビ夫人、美空ひばりがいかにおっかない世界に身を置いているかがわかる。 笹川良一にも触れているのだがさてさて糸山先生は今後のJALをどうお考えなのやらとかそんなことを考えながら読むとおもしろい。
明らかに糸山先生の話題をこの章は外した気がする。 21世紀を迎えて新たなるタブーの解禁に挑戦しているように思えた。 おもしろい。
おもしろい。
おもしろい。 もっと分厚くして欲しい。
|
|

[ 文庫 ]
|
黒幕―昭和闇の支配者〈1巻〉 (だいわ文庫)
・大下 英治
【大和書房】
発売日: 2006-03
参考価格: 800 円(税込み)
販売価格: 800 円(税込)
中古価格: 80円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・大下 英治
|
カスタマー平均評価:  4 4
 政財界、マスコミ、ヤクザにまで影響力を持った「最後のフィクサー」の生き様を知る。 政財界、マスコミ、ヤクザにまで影響力を持った「最後のフィクサー」の生き様を知る。
「昭和闇の支配者」シリーズの第一巻は、「黒幕」児玉誉士夫の生涯を描く。「修羅の群れ」で著名な大下英治の書下ろし。戦中から軍人や政治家に食い込み、戦後はその人脈を財界やマスコミ、ヤクザにまで拡大し、黒幕として日本を支配していく様は圧巻である。言葉を選ばなければ、ダーティーヒーローといったところか。児玉の名前を知っていても、その生き様については知らない人も多いのではないか。児玉と小佐野賢治はもちろん、笹川良一、田中角栄と深い関わりを持つ。さらには中曾根康弘、渡辺恒雄、氏家斉一郎等との関わりがあったことをこの小説ではじめて知った。善悪はともかく、日本を裏面から動かした児玉の手腕と度量は凄かったのだと素直に思った。
 児玉誉士夫のことを知りたいなら 児玉誉士夫のことを知りたいなら
立花隆の 田中角栄研究がいいかと 大下先生の この本は 基本的なことは 押さえてますが あくまでも講談本かと。
それにしても ここに出てくる 野口宏さんって ラテンクオーターの 用心棒だった 野上宏さんですよね?
なんで 仮名?なんでしょうか?
 昭和の闇 昭和の闇
ロッキード事件で有名な児玉誉士夫の生涯を描いたノンフィクションです。児玉誉士夫の名前は聞いたことがあっても、どういう人か知っている人は、一般の人では少ないのではないでしょうか?この本を読むと児玉誉士夫が、昭和の闇の支配者であったことがよくわかります。その迫力が伝わってくるように思います。その底力に大変興味を持ちましたし、人間としての度量の大きさに感じ入りました。よく知った事件の裏側についての理解も深まりましたが、読んでいると何だか怖くなりました。
 児玉氏を知る手がかりとなる1冊です 児玉氏を知る手がかりとなる1冊です
ロッキード事件をはじめ、様々な事件を読むに付け、必ずといってよいほど、児玉氏の名前が出ることから、一体、どんな人物なのだろうと興味を持って、購入した本です。読んでみてわかったのは、ロッキード事件は、ほんの氷山の一角にすぎず、「事件の影には児玉あり」という言葉が誇張でないと思われるほど、多くの事件に関わっているということ。
この類の本の場合、情報量が決め手になるのですが、類書では、「昭和の黒幕」といったタイトルで複数人を、1冊で扱っていることが多いのに対し、このシリーズでは、各巻ごとに、1人の主人公を中心に扱っており、そういった面での不満が、解消されています。ただ、1冊で扱ったとしても、まだまだ、氏について知りたいと思わせるのは、よほど、多くの事件に、児玉氏が関わったことの裏返しといえるでしょうか。
児玉氏を知る手がかりに適した1冊です。
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和 (平凡社ライブラリー (150))
・網野 善彦
【平凡社】
発売日: 1996-06
参考価格: 1,223 円(税込み)
販売価格: 1,223 円(税込)
中古価格: 799円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・網野 善彦
|
カスタマー平均評価:  5 5
 網野史学の出発点 網野史学の出発点
本格的な歴史の学術書。「日本の歴史をよみなおす」や「蒙古襲来」といった啓蒙書とは一線を画すものがある。つまり、記述の根拠となる資料を示して、その著者による読解を通じて結論を示す、というスタイルなので、分かりやすさや通俗的面白さを期待してはいけない。
内容は、平泉澄が先鞭をつけたが、途中で研究を放棄してしまった、日本における「アジール」の研究である。著者は、日本においては寺や市場、自治組織などに法の及ばない「アジール」が存在したことを各種資料を駆使して示そうとする。
この指摘は、暗黒の時代のように考えられている中世において、むしろ江戸期よりも庶民には権力に対する抵抗の自由があったことを示唆していて興味深い。しかし、それは一方で俗界からの「無縁」を条件とする厳しいものでもあった。
よく知られているように、この「為政者に抗して自由を求める『道々の者』をテーマに小説を描いたのが隆慶一郎である。その点、痛快な歴史小説を生み出す原動力になったことは評価できる。また、この書物でははっきりとは打ち出されていないが、「無縁」を天皇とダイレクトに結びつける視点を後年の網野氏は打ち出し、それがかたちを変えた天皇崇拝ではないか、と一部からは批判された。
いずれにせよ、本書は大変独創的な網野史学の原点であることは間違いない。必読の歴史書である。
 民俗の歴史学は本書で始まった 民俗の歴史学は本書で始まった
惜しくも、物故された歴史学者、網野善彦氏の網野歴史学とでもいうべき史学の代表作である。日本でも欧州でも中世は宗教の支配する暗黒の時代と認識されていたが、本書によって、網野氏は日本の中世の封建時代の中の農民や武士以外の人々の生活を克明に調べ上げ、駆け込み寺に代表されるような、当時の体制から、切り離された自由の空間があった事を指摘する。本書によって日本の歴史学も、支配階級・制度の闘争と変遷から庶民の暮らしが研究の対象として切り拓かれていった。柳田国男が民俗学を作ったように、網野氏は民俗歴史学を作り上げたのだと思う。
 日本中世の自由とは何か 日本中世の自由とは何か
網野善彦といえば、まず「無縁・公界・楽」が挙げられるという網野氏の代表作。
網野史学を理解するなら、まずこの本を読まねばならない。
網野氏の専門は中世史であるが、この本は中世のみに留まらず、未開社会から
近世までを倒叙的に叙述してある。また、その問題関心は網野氏自身「風呂敷」
と称したように幅広い。その起点は「自由」である。
西洋近代の言う「自由」とは異なる意味において、日本中世に「自由」が成立
したとする。しかしながら、そこには「平等」ではない「階級」が存在したと
している。近年の矮小な「差別論」など、たちまち崩壊するであろう。
また、「二十二章 未開社会のアジール」では、アジール(避暑地、または避難所
と訳される)論を未開社会に広げて適用することを提起する。もともと、アジール
論は平泉澄が主張したものである。「皇国史観」でもって否定されこそすれ、
正当に論証されてこなかった平泉を正当に批判したことに、この章の意義がある。
 「自由」をつきつめるのなら 「自由」をつきつめるのなら
日本特殊性論の流行はなお衰えを見せていない。とは言っても、それは結局、特にアメリカを強く意識した、文化の差異化であるが。 そんな中で例えば「自由」という理念はヨーロッパ産のもので、我々には彼らとちがう文化、いわば、日本式の自由があるという。たしかに「自由」はもともと仏教用語であり現在とは全くニュアンスが違ったものであって、それをfreedomの訳語として(たしか福沢諭吉が)採用したのである。 しかしそこで明らかにされないのは、日本にもともとあった「自由」とはなんなのかということ。日本特殊性論の論者たちは、つきつめていえば、このことを明らかにしようともしていないのではないか。なされるのは「日本は○○とは違う」といった、否定論の反復のみである。 前置きが長くなったが、その問いに答えているのが本書かもしれない。たしかに網野は楽や公界をユートピアとして提示してはいる。しかし彼の描き出す中世社会の「自由」には、現代の我々が簡単にそのノスタルジーを投影することはできない。なぜなら、(一つだけネタバレしてしまうが)その自由は、「無主」という生き方でしか達成できないものだからだ。 もう一言。説得力ある歴史感をたてるには、実証だけでもなく、思想だけでもなく、その両方が必要なのだと、この本に教えられた。
 中世史のコペルニクス的転換 中世史のコペルニクス的転換
ここで述べられているのは、中世史のコペルニクス的な転換。ネガティブなイメージのある「無縁」という言葉は、徴税される義務などからの縁を切る、という意味のポジティブな意味合いを持ち、「駆け込み寺」のように、公権力の及ばない場所に逃げ込めば、縁を切ることができる、という救いへの希望であり、西欧などでもあったアジ―ルにほかならない、と。無縁坂なんていう場所の名前は今でも残っているが、坂とか河原とか、境界のような場所は日常空間ではなく、古代からの残されたきたような意識を働かせれば、それは神の宿る場所でもある、と。 そして、海や山などは昔から入会権を認められていたけども、そうした無縁という原理が生きる場所が公界(くがい)である、と。互いに独立した人格を持つ自由人として、パブリックな場所で生きていった人々はいたし、能役者や桂女などの生き方はまさにそれだし、ある狂言には登場人物が殴りかかられそうになると「公界者に手をだすとはなんと無体な!」と非難する場面もあり、後の河原者のようなネガティブなイメージではない、と。そして往生楽土、楽市楽座という言葉に残る「楽」って言う概念はユートピアそのものだと筆を進めていく。 その中で、改めて考えさせられたのが「勧進」という概念。これは橋をつくるとか、港の浚渫工事をやるための資金を集めるためのシステム。「勧進帳」で弁慶が白紙の巻紙を読みながら、勧進のために諸国を回っている山伏なんだ、と富樫にシラを切る場面があるが、そうしたシステムが中世にはあったし、出来たインフラは公界であり、それを維持するために関所料金などを徴収していたのは無縁の人々だったという展開は素晴らしかった。
|
|

[ 文庫 ]
|
明治大正史〈世相篇〉 (講談社学術文庫)
・柳田 国男
【講談社】
発売日: 1993-07
参考価格: 1,418 円(税込み)
販売価格: 1,418 円(税込)
中古価格: 795円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・柳田 国男
|
カスタマー平均評価:  4 4
 日本の社会史を学べる本 日本の社会史を学べる本
本書を読んで、自分があまりにも過去の日本人のくらしを知らないということを思い知った。また、なんとなく遠い昔から続いてきた日本の伝統と思っていた事柄が、明治大正のいわゆる近代になって普及したものが非常に多いということも知った。著者は明治大正期の世相をもっとも映し出していると思われる過去の新聞記事を約1年間にわたって眼を通し、それに執筆当時(昭和5年)の著者がありふれた事実と捉えていた事柄を援用して、明治大正期の常人の日常生活を細部にわたって解説していく。明治大正60年間に起こった常人の生活の変遷を、固有名詞をできるだけ避けて私たちの眼前に現れては消える事実のみで描き出そうとする著者の試みは、文体としては冗長で退屈に感じる部分もあるが、執筆当時においては全く新しい社会史の試みであり、なおかつ現時点からみれば明治大正期の一般庶民の暮らしを知ることができる貴重な記録になっている。ただ解説でも触れられているように、日本人の生活様式が激変した高度経済成長期以降の世代である私にとっては、意味が理解できない箇所も多々あったので、詳しい注を付けて貰えればなおよかったと思う。
|
|

[ 文庫 ]
|
完訳フロイス日本史〈1〉将軍義輝の最期および自由都市堺―織田信長篇(1) (中公文庫)
・ルイス フロイス
【中央公論新社】
発売日: 2000-01
参考価格: 1,200 円(税込み)
販売価格: 1,200 円(税込)
中古価格: 800円〜
( 通常3〜5週間以内に発送 )

|
・ルイス フロイス
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 総タイトルが問題だが、きわめて貴重な資料。 総タイトルが問題だが、きわめて貴重な資料。
たいへんな労作で、同時代の資料として貴重であるのは間違いない。
ただ、これに『日本史』というタイトルが付いているのが問題だ。
いかなる歴史書も、書き手の主観を排除することなどできないが、
それでもここまであからさまな主観(異教徒から見れば偏見)で徹底されているならば、「日本史」という看板は下ろすべきだろう。
実態は、一人の宣教師の滞日数十年間を綴った「手記」であって、
たとえば同時代の日本人のものでは山科言継『言継卿記』や、吉田兼見『兼見卿記』、勧修寺晴豊『晴豊公記』などと同列の「日記」である。
フロイスの上司にあたるバリニャーノから「冗長すぎる」として公的記録としては評価されなかったようだが、
個人の「日記」としてとらえれば、むしろそこにこそおもしろさがある。
一宣教師にすぎないフロイスが、気負いに気負って、信長を始めとする名だたる武将や堂上公卿と交流し、彼らを評するくだりなどは、他の資料では見えない面が浮かび上がってなんとも興味深い。
好意も悪意も、ここでは隠す必要がないから実にあからさまで、だからかえって事実関係に嘘はないと逆に判断できる。
本書の値打ちは、この「偏見」にこそあるだろう。
 年よりの暇つぶし 年よりの暇つぶし
カソリック宣教師の、優越感蔓延の本です。いかに、フロイスが、「日本人は勤勉で知的な民族である。」と書こうとも、言葉の端々から、「このサルどもめ!」という匂いがプンプンと漂ってきます。
ただ、日本人が知っている(と思っている)室町安土桃山時代を、別の視点から見させてくれます。この時代の風俗を、西洋のの視点から説明してくれているので、おもしろいし、興味深いものです。我々日本人が当たり前として見過ごしていた室町安土桃山時代の風俗を改めて認識させてくれます。
問題は、これを歴史書としていいかどうかなのです。歴史の資料としてはかまいませんが、これを歴史書とするには問題があると思います。
私のような、年よりが暇つぶしにこれを読むのはかまいません(私は、実際暇つぶしの時に読んでいるので全12巻読み終えるのはいつかわかりません。)が、若い勉学中の方は、よりまともな歴史書を読むことをお勧めします。(はっきりいいますと、全体の基調は、「異教徒は非業の死を遂げて当たり前」、「クリスチャンは神に守られ、たとえ死んでも、それは神に嘉せられてゼウスの意志によって恩寵を受け天国に参らせられる。」という論調です。)まともに、読む本ではありません。くれぐれもこの本で歴史の勉強をしようなどとは思われませんように。
ただ、この本を完訳された翻訳者の方々の努力は刮目すべきものです。この訳業によって、我々のような、語学に稚拙な者でも、中世の西洋人の考え方がわかるのですから。まともな、原稿がない状況で、それを、丹念に収集し、かつ、まとめ上げて翻訳するということは、尋常な努力ではなせなかったと思います。その点はすばらしいと思いますし、このような本は滅多に出てこないと思います。絶版にならないうちに買っておくこと(たとえ今すぐ読まないとしても)をお勧めします。
 戦国時代を知るための必需資料 戦国時代を知るための必需資料
ポルトガル人が書いた日本の戦国時代を知る超一級の資料。外国人の目から見た日本は、時として偏見に支配されているものの、人々の生活や信長との会見とその人ざまを生き生きと描いている。比較的無味乾燥になりがちな日本側の資料を補い、戦国ロマンを書きたてる書である。原資料の順序を変え、トピックごとにまとめたことにより読みやすくなっている。 残念なのはこの文庫版が作られるにあたって、ハードカバーにあった訳注などが削られてしまったことであるが、それでも十分な歴史資料であるし、この手の一次資料として破格の安値となっているのがうれしい。
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
なぜ偉人たちは教科書から消えたのか 【肖像画】が語る通説破りの日本史
・河合 敦
【光文社】
発売日: 2006-06-23
参考価格: 1,365 円(税込み)
販売価格: 1,365 円(税込)
中古価格: 439円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・河合 敦
|
カスタマー平均評価:  3 3
 歴史上の偉人達の知られざるエピソードを楽しむ 歴史上の偉人達の知られざるエピソードを楽しむ
歴史学上の新しい発見に伴って、教科書も少しずつ内容を変えていきます。源頼朝や足利尊氏などの肖像画が、どうも違う人物を描いたものらしい、ということが分かり、教科書から肖像画が消えています。
本書は、偉人たちの肖像にかかわるあれこれをネタに、偉人達の知られざるエピソードを紹介してくれる歴史雑学本です。
河合氏の本を読むのは初めてでしたが、たくさん本を出しておられるだけあって、読者のツボを心得ておられますね。
「へぇー」、「ほぉー」、「あはは」と笑っているうちに読み終わってしまいました。
源頼朝の肖像画と思われていた人物が、どうも違う人らしい、と言われるようになりました。教科書には「伝源頼朝」というキャプションが付くようになり、そのうち、肖像写真自体が削除されてしまいます。
聖徳太子や武田信玄、近いところでは西郷隆盛も、本人の顔だちを伝えるものではなくなりました。
……という内容は、書名からも想像することですが、本書は、これとは逆に、テレビの時代劇でおなじみの「水戸黄門」や「大岡越前」や「暴れん坊将軍」の肖像画を示し、テレビのヒーローとずいぶんイメージが違うことも示しています。
特に「遠山の金さん」の晩年の姿を描いた肖像画は強烈でした。もちろん、西郷輝彦や松方弘樹の顔とかけ離れていますので、時代劇ファンにはショックかもしれませんね。
著者も「歴史の厳しい事実というものを突きつけられる」と言っていますよ。
他に、
「大岡裁きの87の逸話のうち84は江戸時代以前の物語からの引用」
とか、
「徳川綱吉の生類憐れみの令は、捨て子や子殺しを禁止する法令や、
社会福祉政策の一環だった」
「日野富子は応仁の乱の要因をつくったと言われているが、主要因で
はない」
など、歴史上のヒーローと悪役の評価が逆転するような新説も紹介しています。
 日本史が不得意な人はどうぞ。 日本史が不得意な人はどうぞ。
映画や小説と史実とを区別できない人にはお勧めです。日本史が好きで自分なりに調べたりしてる人には、文献の意見の羅列でつまらないでしょう。地道な作業を省いて、お手軽に本を作るとこうなる見本です。
 テーマは面白い テーマは面白い
多くの偉人の肖像画に関する謎を学術的に丹念に探索していく内容には頭が下がる。しかし、最終的にどの偉人も同じような切り口の繰り返しになってしまった感が否めない。題に引かれたが、タイトル負けという感じもする。もっと軽くして多くの偉人を取り上げるか、絞るかした方が良かったようにも思う。著者の努力には脱帽。
|
|

[ 文庫 ]
|
NHKその時歴史が動いた―コミック版 (激動幕末編) (ホーム社漫画文庫)
・NHK取材班 ・萩原 玲二
【ホーム社】
発売日: 2004-09
参考価格: 920 円(税込み)
販売価格: 920 円(税込)
中古価格: 297円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・NHK取材班
・萩原 玲二
|
カスタマー平均評価:  4 4
 このシリーズいいですね♪ このシリーズいいですね♪
幕末はやはり日本の歴史の中で戦国時代に匹敵するほど
おもしろいですね。
思想と思想のぶつかり合い。
大和を愛する熱き魂。
日本史の入門にも最適です。
是非一読を
 内容は、とても面白いけれど。 内容は、とても面白いけれど。
絵がダサい
|
|

[ 単行本 ]
|
図説 歴史で読み解く京都の地理
・正井 泰夫
【青春出版社】
発売日: 2003-10
参考価格: 1,050 円(税込み)
販売価格: 1,050 円(税込)
中古価格: 909円〜
( 通常3〜5週間以内に発送 )

|
・正井 泰夫
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 値段以上に良くできた本 値段以上に良くできた本
まず、この内容の書籍が1000円であることに驚かされる。
見開きごとに解説と地図がセットになって読み解いていく体裁をとっており、2色刷りが若干残念ではあるが内容の豊富さを考慮するとお買い得であると言える。
京都盆地が湖であった太古から現代に至るまで、日本史の中心であり続けた京都を、歴史の1ページごとに丁寧に解説している。古代の都から安倍清明、三大葬送地、西国三十三所、京都七口、東山三十六峯、伝統産業、京野菜、大火と地震、太秦、路面電車路線図、現代の祭りにいたるまで、まさに京都特集の本でなければ読めない内容がコンパクトに一冊にまとまっている。
過去から現代の京都に興味がある向きには、無駄にはならないばかりか、歴史小説などを読み解く際にも横においておきたい書籍である。もう少し高くても良いのでカラー刷りであって欲しかったと思わせる内容。
 書名に偽りなし 書名に偽りなし
本書は今どきのムックには珍しく2色刷のみ。よってパッと見た目のヒキは
弱いのですが、内容は非常に濃く、満足できます。これでこの値段は安い。個人的には、古代から新撰組までを時代を追って考察している(もちろん、
書名の通り各ページには必ず地図が添えられています)、第一章が楽しい。
その辺の情報は、このレビューの上に書いてある《エディターレビュー》と
《目次》を参照されたい。 同書の《まえがき》にあるとおり、漢字には適当にルビが振ってあって助かります。
しかし、「宇治川」くらいは誰でも読めると思いますが…。
|
|



