|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
戦争中毒―アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由
・ジョエル アンドレアス
【合同出版】
発売日: 2002-10-10
参考価格: 1,365 円(税込み)
販売価格: 1,365 円(税込)
中古価格: 243円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・ジョエル アンドレアス
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 軍事国家アメリカの本当の姿に迫る好書 軍事国家アメリカの本当の姿に迫る好書
アメリカを観光ではなく、「観察」する機会を得たことがある人であれば、
その国力のイメージに反して、教育・医療を受けられない人々の多さ、
圧倒的な貧富の格差、洗脳と呼んでも差し支えのない様な、軍国主義教育を受け続けてきた
「アメリカ一国主義」を疑わない普通の人々。
支配者階級が非白人系国民に、ときに見せるあの猛禽類のような目。
・・・それらを肌で感じることができただろう。
独立を勝ち取った、言い換えれば自分たちの運命を決める権利を勝ち取ったアメリカ人は、
他のすべての人々の運命もアメリカ人が決めれると思った。いわゆる「運命顕示(manifest destiny)」である。それがアメリカという国のすべてのスタートだった。
一分に100万ドル、一家に年間4000ドルの軍事費用が発生するアメリカ。
戦争の裏で不幸のどん底に落とされるのは、どの時代でもどの国でも、弱者なのだ。
かつて誰かが「アメリカの正義には必ず暴力が伴う」といったが、
本書のタイトル「戦争中毒」と呼んだ方が適切であろう。
アメリカは変わるか?変えられるか?
世界の平和と人々の幸福を考えるとき、この国のことは避けて通れない。
この本では、小生が長年に渡って少しずつ学んできたものがまとめて紹介されている。
おぞましい「権力の魔性」を概観することができる。
この本の裏表紙にブレイズ・ボンペインという”オフィス・オブ・アメリカ”の
ディレクターが書いているように、「(アメリカの)軍国主義崇拝について12年間の
初等中等教育で学ぶ以上のことを学ぶだろう」に納得する。
この言葉を和訳されたこの本の読者に贈っても間違いはないと思う内容である。
 富獲得のためには、手段を選ばない国 富獲得のためには、手段を選ばない国
富獲得のためには、戦争をも厭わないというハイリスク・ハイリターンの原点が
ここにありました。本書を読むと、アメリカは何故戦争を遂行するのか、戦争で
どんなことをして、どのように富を拡大してきたか、TV新聞などのマスコミでは
殆ど報道されることの無い、隠れた一端を窺い知ることができます。アメリカに
とって戦争とは、富獲得の手段であって、その手段にタブーはありません。イン
ディアンたちの虐殺に始まる建国と領土拡大、現在の石油利権獲得に至るま
で一貫していることが浮かびあがります。余談ですが、2大政党制が確立され
た民主主義国家と言われていますが、戦争による国富拡大のイデオロギーは
共和党も民主党も違いなく、共通しています。
 インディアンから911までの軍拡主義を中学生でもわかるように説明。日本人がアメリカでの再販に大きく影響。 インディアンから911までの軍拡主義を中学生でもわかるように説明。日本人がアメリカでの再販に大きく影響。
この本は、インディアンたちの虐殺から始まって、911まで、アメリカがいかに戦争によって強引に国力を広げていったか、そしてそれが世界に与えた混乱と、国民にまわったツケを、非常にわかりやすく漫画でかかれている。
もうあまり話題にもならないカーター、レーガンたちの時代のイラン・イラク戦争等もうまくまとまっていて、いまさらながら「あ?そうだったのか」と納得。レーガンが、GEのコマーシャルで雇われた役者だったとか、元副大統領のチェイニーが、石油掘削会社の社長だったとかとんでもない事実もいろいろでてくる。
加えて、この本がでてきた経緯もおもしろい。いったん絶版になったものを発掘し再販。その再版に、きくちゆみ氏と有志達が賛同し資金を提供したのだ。これによってアメリカ国内でこの本が読めるようになり、いまでは学校などでも参考書としてとりあげられているという。
日本人がアメリカ人の目を覚まさせることに影響を与えているのだ。
 あらためて一挙にかかれるとやはりショック あらためて一挙にかかれるとやはりショック
この本が2003年度版のまえがきにもあるとおり、いち早く日本語訳されている
とのことを知りほっといたしました。
また、ここに書かれていることは、ごく一部を除いては、映画や個人レベル
の会話では見聞きしてきたものでした。
しかし、一挙にこう漫画にされると本当にショック。
でも、一番傷つくのは一般のアメリカ人達だと思います。
この本はきっと、憤りとともに、こういう世の中「なんとかしたい」という情熱をもって
かかれたもの。
読んだ人が何を感じるかを自分なりに味わって、自分なりの意見を持つきっかけになる
のではないかと思います。「人として何が許せないか」、きちんと考えて、自分なりに感じ
るとともに、いろいろなものをみたり、読んだり、経験しながら、客観的な態度を
身につけたいと思いました。
何が起きるかわからないという感想をもつと同時に、改めて、戦争は嫌だと思いました。
 この本の原作がアメリカで普及することを望みます。 この本の原作がアメリカで普及することを望みます。
マンガですので簡単に読めますし、丹念に調べられた史実に元ずき書かれているので、
アメリカの帝国主義・戦争(侵略)の歴史の概要が理解できます。
僕が、特に感じたのは、マニュフェストデステニー(manifest destiny)
「キリスト教徒による新大陸の獲得と開拓を神に与えられた明白な使命」とする考え方、
この考え方を拡大解釈していくと何をやっても正当化されることになってしまわないかと....
恐ろし事です。
最近読んだ「アメリカの鏡・日本」へレン・ミアーズ著も一緒に読んで見られると歴史に対する洞察力を
養うのに良いのではと思います。
この本、原書がアメリカで反戦活動家中心に2万部売れたとの事ですが、もっと普及して
草の根運動から大きなうねりになると良いですね!
|
|

[ 文庫 ]
|
虜人日記 (ちくま学芸文庫)
・小松 真一
【筑摩書房】
発売日: 2004-11-11
参考価格: 1,365 円(税込み)
販売価格: 1,365 円(税込)
中古価格: 998円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・小松 真一
|
カスタマー平均評価:  5 5
 ぎりぎりの状態での自分の態度を想像すること ぎりぎりの状態での自分の態度を想像すること
この日記の史実資料としての意義については、山本七平氏「日本はなぜ敗れるのか - 敗因21ケ条」に詳しいですが、当時の軍部の情報を多く持つ立場でありながら、民間人(軍属)として比較的利害関係のないポジションで冷静な観察ができている、といった点は確かに一読すれば窺い知ることができます。本書の意義に限らず、その背景、分析などについては、「日本はなぜ敗れるのか」に余りに的確で詳しく考察されています。一方、個人的に感じたことは、極限状態での人間の実態はこうも惨めでむごいものか、ということでした。本書でも山口大佐という立派な将校の話(比人からの信用も絶大、信念の強い人であり、馬鹿な閣下の命令には決して服さず敬礼もしなかったという)が紹介されていますが、こうした人は本当に稀だったのでしょう。確かに生死を賭け、「最後の食料を他人に差し出せるか」といったぎりぎりの問いに、明確に答えられる自信は少なくとも今の僕にはありません。本書の語り口は淡々としているだけ、人間の「弱さ」というものをつくづく考えさせられます。 山本氏も書いていますが、こうした極限状態を生み出さない、といった努力がまず求められることであり、極限に近づくにつれ残された選択肢は狭く、恐ろしく辛いものになってしまう、ということを、本書を読むことによって痛感 = 追体験します。また、ぎりぎりの状態での自分の態度というものを想像し、その緊張感を普段の生活の中で意識することは、間違いなく通常の自分の生活態度や人間関係を見つめ直すひとつの視点になります。
 戦争や収容所の実態、極限状況下での日本人を的確に記す 戦争や収容所の実態、極限状況下での日本人を的確に記す
ジャーナリストがジャーナリスティックに走りすぎ、事実を歪めた報道を行った例は枚挙にいとまがない。それどころか、単なる伝聞をいかにも自分の目で見たかのような記事に仕上げたり、全くの虚構と言う例もある。それらとは反対に、本書はジャーナリスティックにならず、見たことを感じたことをありのままに書き連ねている。本書で一番評価されるべき点はここにあると思う。 ここに書かれていることは一軍属が体験したことに過ぎないが、先入観にとらわれたジャーナリストが書いた記事より、戦争や収容所の実態、極限状況下での日本人と言ったものを的確に捉えていると思う。
 奇跡の観察記録。悲惨の渦中で科学者の目は何を見たのか 奇跡の観察記録。悲惨の渦中で科学者の目は何を見たのか
終戦間際、著者はブタノール製造を任務とする文官としてフィリピンへ赴く。
そこで日本軍の敗退、ジャングルでの彷徨、そして終戦。投降とその後の捕虜
収容所での生活を体験する。事態のただ中に身を置きつつも、科学者としての
冷静な観察がなされ、余計な修飾を廃した稀有な記録が残されることになった。
本書を世間に知らしめた山本七平氏はその価値をこう紹介している。
「戦争と軍隊に密接してその渦中にありながら、冷静な批判的な目で、しかも
少しもジャーナリスティックにならず、すべてを淡々と簡潔、的確に記してい
る。これが、本書のもつ最高の価値であり、おそらく唯一無二の記録であろう
と思われる所以である。」
また山本氏は解説のなかで、投降後の捕虜収容所で、ジャングルを生き抜いた
屈強な男達が、いともた易く一握りの暴力団的グループの配下に組み込まれ、
コントロールされていく様を記した部分にふれ、現在の問題としてもなお生き
ているという。確かにその通りだろう。国民必読の書。
 待望の復刊、深い感銘 待望の復刊、深い感銘
山本七平「日本はなぜ敗れるのか」を読んで以来、そのベースと
なった本書をぜひ読んでみたかったが、このたび復刊が実現し
期待を持って読んでみた。
本書は著者がフィリピン戦線で体験した日本軍の行動が率直に
語られている。また日本軍に従って戦った朝鮮人、台湾人、
フィリピン人のことも語られている。もちろん勝者の米軍に
ついてもだ。個々の話はどれも心を打つ。食糧が尽きた
日本兵が友軍同士殺し合ってその肉を食う話、ウジの涌いた
母親の死体にいつまでも取りすがっている幼児の話、
栄養失調のため温泉に入ったとたん心臓麻痺で死んだ兵士の
白骨が累々と温泉のなかに沈んでいた話などフィリピン
戦線はここまで悲惨だったのかと改めて思い知らされた。 さらに捕虜収容所での数々の体験と見聞が著者の人間観察を
さらに深くする。収容所では戦場以上に人間の醜い面が露呈する。
著者は戦場と捕虜収容所での体験から人間とは何か、
日本人とは何か、そして大東亜戦争の敗因(敗因二十一箇条)は
何かを冷静に考え、それを数冊の手帳に記し、骨壺に隠して
日本に持ち帰る。 敗因二十一箇条のうち、日本の不合理性、米国の合理性、
精神的に弱かった、克己心の欠如、反省力なきこと、
個人としての修養をしていないこと、独りよがりで同情心が
ないこと、日本文化の確立なきため、日本文化に普遍性なき
ため、などは今日の日本の姿であり60年前と少しも
変わっていない。 本書は会田雄次「アーロン収容所」と同等あるいはそれ以上の
地位を占めるべきと言っても過言ではない。
本書は大東亜戦争を日本によるアジア侵略と見る人にも
日本によるアジア解放と見る人にも、またそれ以外の人にも
お薦めの書である。
 日本人の反省 日本人の反省
先ずは、この、虜人日記がちくま学芸文庫として再販されたことを祝いたい。
しばらく忙しさにかまけて読了できないでいた「日本はなぜ敗れるのか」を閉じることができたたその日に虜人日記の再販を知ることになった、天啓が降りたような気分である。山本七平氏をして「日本はなぜ敗れるのか」を出筆せしめるに至った虜人日記をついに読むことができる日がこようとは。
先の大戦から半世紀を大きく過ぎ、語り部となられた方々も多くが去られる中、虜人日記はただその戦況の壮絶さや戦場の悲惨さを語るのではなく、冷静な分析を持って極限におかれ露呈した日本人の真相を私たちに残してくれたのだ、小松氏の予言とも言える日本を見る目は、今日本が自らの道を自らで決めなければならないこの時代に今一度自らが何者であるのかを問い直すための鏡になってくれるだろう。
日本の敗因、日本人の暴力性などの小松氏の分析はひごろから私が日本に抱いていた「日本人は自然に非合理なもを合理性と自分たちが思い込んでいる非合理によって黙殺するのではないか」「公的のものも含めて日本における権力というものは総じてやくざ的構造を帯びてくるのではないか」などの疑念を確信へと導いてくれた。
虜人日記再販に尽力された諸兄に感謝しつつこの文を終わりたい。
戦争を反省することに疲れ果てた日本人に問う、私たちは本当に反省してきたのか?
|
|

[ 単行本 ]
|
アフガニスタンに住む彼女からあなたへ―望まれる国際協力の形
・山本 敏晴
【白水社】
発売日: 2004-08
参考価格: 1,470 円(税込み)
販売価格: 1,470 円(税込)
中古価格: 279円〜
( 通常2〜3日以内に発送 )

|
・山本 敏晴
|
カスタマー平均評価:  5 5
 国際協力に関心のある方には必見 国際協力に関心のある方には必見
山本氏の理系らしい整理された文章と、シビアまでに冷静な観察眼、そして何よりも、真の国際協力のあり方を伝えようとする情熱がほとばしる力作。暗くなりがちな場面でも、ウィットに富んだ表現が、読み続ける力を与えてくれます。
 Think global, Act Local Think global, Act Local
日本医療救援機構(MeRU)でアフガニスタンにいった日本人男性医師の活動記録。
表紙写真からいかにアラブの女性が迫害されているか語るのかと思っていたら、まるで違う。
信じられないほど大らか。コミック調の寸劇ドラマやちょっとエッチな話題を入れ、
「にこにこ妖怪ナジーム」、頼りない味方のムーミン、ペテン師ファウルと
登場人物も漫画っぽく描かれている。
ボランティア活動は茶化してはいけない領域であるし、事実やっている使命は重いのだが、
しかめ面してうんうん聞くより、肩の力をぬいて見わたす姿勢は受け入れやすい。冗談のようだが、アフガニスタンでは乳児がむずかると麻薬を与える習慣がある。
小学校にすら行っていないということは一般常識もなく、自分の国がどこまであるのか知らず、
外国すべてをアメリカと考えたりするというのだ。
山本氏は衛生観念、義務教育、人口問題、環境問題、経済格差といったものがすべてボランティア活動には
絡んでくると語る。
貧しいから物資がないと思い込んでいる日本人。だがアフガニスタンは東西交流の地として
栄えた歴史が語るように、周囲の国から物資を買う経路はある。隣国イランはアラブの先進国。
皮肉にもアフガニスタンに入る外資は、外国人のいる地域(都心部)に偏る。
そしてアメリカ軍がやった大ボケボランティア。知っているつもりでまったく知らなかったことに気付かされる。
ボランティア、国際協力に興味があるならまず読んでみることをお勧めします。
 本当の国際協力とは… 本当の国際協力とは…
この本を読んで、本当の国際協力ってどんなふうなんだろうということを改めて考えさせられました。
私達が出来る具体例がいくつか書かれているので、ぜひ読んでみてください。
 みんなに読んで欲しい本 みんなに読んで欲しい本
泣く本というより、考えさせられる本です。まずこの本を読んでアフガニスタンという国をみんなも知って欲しいです。それから本当の国際協力とは何か考えて欲しいです。すごい読みやすくて難しくない本です。絶対に読んで欲しい一冊です。
 「山本敏晴が行く」第2弾です。 「山本敏晴が行く」第2弾です。
第一弾、シエラレオネに続く「山本敏晴が行く」第2弾です。今回も明るく楽しくまとめてらっしゃいます。NGOが狙われるようになった原因は米軍の広報活動にあった。という事実に私はショックを受けました。つまり、米軍がイラク戦争を正当化しようとキャンペーンを実施した所、NGOは米軍の一味と現地の人が受け取ったため、NGOが満足に活動できなくなってしまったという事です。NGOにとっては,中立の立場を守る政治的な努力がより難しくなってしまいましたね。
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
天使 (Truth In Fantasy)
・真野 隆也
【新紀元社】
発売日: 1995-02
参考価格: 1,835 円(税込み)
販売価格: 1,835 円(税込)
中古価格: 290円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・真野 隆也
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 天使について簡潔にまとめられています。 天使について簡潔にまとめられています。
一番有名な天使達、堕天使達と、天国、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教について等が分かりやすく簡潔に紹介されている本です。気取った説明ではなく、親しみやすさが感じられて初心者向けから結構詳しい方まで気軽に読めると思います。読みやすいので早く読めると思います。
 あやうきものたち あやうきものたち
オカルト系、ファンタジー系のゲーマーにお勧め。
天使のランクや、司る能力など、軽く読める一冊。
『堕天使』と一緒に読みましょう(笑)。
 天使の資料として 天使の資料として
この本は,まず有名な四大天使の説明から始まり,いろいろな天使を紹介しています.プロフィールだけでなく章ごとに,堕天使のプロフィール,天使の住む場所,天使の檜舞台,天使のバックグラウンドなどいろいろな説明がされています.純粋に天使の事が知りたいという人だけでなく,挿絵もあるので何かの作品の資料として使うにもよくできていると思います.
|
|
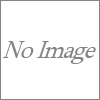
[ 文庫 ]
|
ターンエーガンダム〈5〉月光蝶 (角川スニーカー文庫)
・佐藤 茂 ・富野 由悠季 ・矢立 肇
【角川書店】
発売日: 2000-04
参考価格: 440 円(税込み)
販売価格: 440 円(税込)
中古価格: 1円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・佐藤 茂
・富野 由悠季
・矢立 肇
|
カスタマー平均評価:  4 4
 ターン∀の黒歴史 ターン∀の黒歴史
読んでいてグエン・サード・ラインフォードの役割と、その過酷な境遇に驚きました。ただアニメを先に見てこちらを読んだので、グエン・ラインフォードがモビルスーツに乗っている姿が想像出来ませんでした。家臣の何方かが「紳士は機械人形になど乗ってはいけません」と進言する方、いらっしゃらなかったんですかね‥‥。
惜しむらくは冨野氏ご自身のノベルズを読みたかったです。
 キャラクターの意外な姿・・・。 キャラクターの意外な姿・・・。
スニーカー文庫での最終巻ですが、ディアナの弱い姿やグエンの内面など、アニメでは描かれなかった要素がたくさんでとても驚きました。キャラクターのイメージがアニメの印象とは違い、こちらの面々はギラギラしている?生々しい?等の印象を受けました。また別のターンAとして読めば楽しめる内容ではないかと思います。アニメが大好き!!という方だと「う〜ん・・・」という感想をもたれるかもしれませんが、ターンAのファンの方なら読んでも損は無いと思いました。
|
|
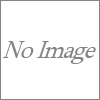
[ 単行本 ]
|
バンド・オブ・ブラザース―男たちの深い絆
・スティーヴン アンブローズ
【並木書房】
発売日: 2002-05
参考価格: 2,100 円(税込み)
販売価格: 2,100 円(税込)
中古価格: 735円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・スティーヴン アンブローズ
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 第二次大戦ヨーロッパ戦線のアメリカ兵士たちの記録 第二次大戦ヨーロッパ戦線のアメリカ兵士たちの記録
第二次大戦ノルマンディー上陸後のヨーロッパ戦線に投入された第101空挺師団のE中隊。
アメリカ陸軍の中で最も強いといわれたこの中隊の兵士は、アメリカ国内で志願してきた一般の若者を中心に組織されていた。
どうして、この兵士たちが、ここまで強く戦えたのか、という動機の元に、中隊の訓練から、戦闘投入、様々な戦闘を描いたもの。
日本よりも、はるかに物質的に恵まれたアメリカで、そのように兵士を組織し、その士気を高めたのか。また、どのように彼らは戦い、また、どういう状況で能力を発揮したのかという考察をはさみながら、中隊の活動を追ったもの。
 ソベル大尉が気の毒で気の毒で ソベル大尉が気の毒で気の毒で
嫌われ者になってしまっているソベル大尉ですが、好悪は別にしてE中隊を育てた功労者だと
認める中隊員もいるんですよね。身近にいたらわたしも敬遠したくなるキャラクタの大尉です
が惻隠の情を催さずには読んでいられない部分もありました。
良い所も書かれてますが、ヨーロッパでの戦利品獲得についての実情とか捕虜の扱いとか
の件にはやっぱ人間のやる事はアメリカでもソ連でもドイツでも日本でも英国でも同じな
んだよなあ、と思わされました。
太平洋戦争を日本側から描写した数々の戦記、小説とは違った「からっ」とした空気の作品
になってます。だから戦争を知りたいって人が手始めに読むには入り易いかも?
これだけ読めば戦争当事者の事を理解できるってモノじゃないんで、他にも色々読まれた方が
いいのは間違いないですが。
上の文章イタリア抜けてましたね、イタリアもですよ。
 日米の比較において 日米の比較において
ヨーロッパ戦線での米軍の様子が伺え、興味深い内容です。テレビシリーズ
を見られた方も飽きずに読み通されることと思います。
ただ読んで感じるのは、E中隊の死傷率が150%ということでそのすさまじさ
が強調されていますが、それだけ兵士の補充があったということ。孤立した太平洋の島々
で戦った日本軍は、武器も兵隊の補充もなく、死傷率は限りなく100%なのですから。
つまり全滅ということ。
一方、志願した一般市民から成る"市民軍"(職業軍人ではないということ)がいかに
鍛えられ、戦ったのかという組織論的視点を持って読むと、より楽しめる内容ではない
でしょうか。
 涙と感動の最高傑作 涙と感動の最高傑作
第二次世界大戦の小説は数多く出ていますが、これほど細かく兵士一人一人の様子や部隊の様子を書き記した小説は他にそれほど多くは無いでしょう、小説とDVDやビデオをあわせてみるとより深くこの本の内容に触れることができるはずです。厚くて読むのをためらうかもしれませんが一度はまると半分以上は一気に読めます。また、この本は読んでると自分もその部隊の一人のような気がしてきます。
皆さんもこの本を読んで感動とこの世界中を涙で包んだ戦争のことを忘れないでほしいと思います。
 戦争小説の最高傑作 戦争小説の最高傑作
スティーブン・E・アンブローズ氏のベストセラーノンフィクション。これほど戦争を忠実に描き出した本はないといっても過言ではありません。「戦争とはどういったものか」という疑問は誰しも抱いたことがあるはず。そんな疑問の一つの答えがまさにこの作品であるといってよいでしょう。そして本を読み終わった方にも一言。この本を読み、DVDを見て、そこで終わりにしないでいただきたいと思います。そこで感じたことを訳者の上ノ畑 淳一氏が運営・管理しているサイトにも足を運んでください。きっとすばらしい経験ができると思います。
|
|

[ 文庫 ]
|
スターリングラード 運命の攻囲戦 1942-1943 (朝日文庫)
・アントニー・ビーヴァー
【朝日新聞社】
発売日: 2005-07-15
参考価格: 1,050 円(税込み)
販売価格: 1,050 円(税込)
中古価格: 498円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・アントニー・ビーヴァー
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 起こるべくして起こる運命の攻防戦 起こるべくして起こる運命の攻防戦
スターリングラード攻防戦と言えば、凄惨な市街戦や独ソ首脳のエゴによる戦い、
あるいは、ソ連軍の狂気のような兵士の使い方、独第6軍の悲劇と言ったことが思い浮かぶだろう。
本書では、徐々にそこに行き着く要因を詳細な取材によって、
バルバロッサ作戦(ソ連侵攻)・ブラウ作戦(1942年夏季攻勢)から遡り、
追っている戦史書である。
独ソの将官・兵士や一般人など様々な証言で組み立てられ、
そこに著者なりの解釈も加わり読み応えのあるものとなっている。
興味深いのは、軍人として評価の高いマンシュタイン元帥についての記述で、
第6軍の悲劇を招いた張本人としても描いている。
スターリングラードは現在ヴォルゴグラードという地名になっているが、
歴史の証人としてこの地名が復活して欲しいものである。
 グイグイ引き込まれる戦史ノンフィクション グイグイ引き込まれる戦史ノンフィクション
第二次世界大戦の転回点となった、スターリングラードの戦いを
克明に描いた本書。真珠湾攻撃やミッドウェー会戦ならまだしも、最初は
スターリングラードの戦いなんてあまりイメージが湧かないと
思っていたけど、本書はとても読み易いノンフィクションに仕上がってて、
あまり戦史に詳しくない方が読んでも興味深い作品になっていると思います。 淡々とした語り口が逆に戦争の悲惨さを感じさせ、
文章にたくさん引用されている前線の兵士たちの手紙や証言といった
生の声がそれに一役買っています。 単なる戦史ものの枠を超え、戦争が本当に恐ろしいということ、
人が犯してきた愚行の数々など、歴史を振り返る上で色々
考えさせられる内容でした。
 たった60年前にこんな狂気の沙汰が行われていた たった60年前にこんな狂気の沙汰が行われていた
両軍あわせて200万人が対峙し、最終的に包囲されたドイツ軍側だけでも25万人を超えるという史上最大の作戦がスターリングラード攻防戦だ(陸海空の自衛隊を併せても約20万人)。 それはヒトラーとスターリンという独裁者の狂気によって始まり、狂気によって深刻な被害がもたらされた。石油の出るカフカス地方奪取に失敗した時は戦争を終わらせなければならないと将軍たちに伝えていたヒトラーは、カフカス奪取が不可能になると、スターリンという名前を冠した都市を奪取することで、象徴的な勝利を狙うことに方針転換する。国の宝ともいうべき第六軍に満足な防寒具も与えないまま。 一方で、赤軍を自ら粛正してまったことで、弱体化させたスターリンは逆ギレして「1歩たりと後退するな」「恐怖に駆られる者、臆病者はその場で射殺する」という命令を出す。これによって、ソ連軍は脱走兵を射殺する第二戦列を組織し、退却しようとした部隊があれば機関銃を浴びかけたという。こんな無法なことが60年前に行われていたかと思うと、信じられない気がする。
 ロシア人補助兵 ロシア人補助兵
独ソ戦の分岐点となったスターリングラードの戦いを詳細に描いた作品
です。
従来からの資料を纏めた感じで新しい解釈等は有りませんが、驚かされるのは、本来は副次的な目標で有った都市スターリングラードが、ヒトラーとスターリンの思惑により決戦の場と変わっていく事です、その後は、多くの人命の浪費が繰り返されてゆきドイツ第六軍の崩壊、降伏となります。
30万人の捕虜の内、戦後9千人しか祖国ドイツの戻れなかった話は有名ですが、ドイツ兵の中には50,000人ものロシア人補助兵がいた事は知られていませんでした、そしてだれも捕虜になっていない事も。
戦略、戦闘だけでなく、飢えて死んでゆく市民 胴体に爆弾を付けドイツ戦車にぶつかって行くソ連軍用犬の話等読ませる話が多い本です。
戦況を理解できる地図や写真が少なく、広い地域で百万を超える軍隊が戦った状況が分かりずらく何度も読み直す事になりました。 文庫本になって求め易くなりました、お薦めできる本です。
|
|

[ 単行本 ]
|
ベルリン陥落 1945
・アントニー ビーヴァー
【白水社】
発売日: 2004-07
参考価格: 3,990 円(税込み)
販売価格: 3,990 円(税込)
中古価格: 2,049円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・アントニー ビーヴァー
|
カスタマー平均評価:  4 4
 第三帝国の黄昏を冷静に描く 第三帝国の黄昏を冷静に描く
多くの書物が取り上げ、最近の映画「ヒトラー最後の12日間」でも描かれたベルリン攻防戦の最終局面。多くの証言や引用を用い、多角的に第三帝国最後の攻防を描写している。ベルリンの市街戦は言うに及ばず、特にソ連軍の侵攻により多くの被害を被った東プロイセンの状況やオーデル戦線、ハルベ包囲網突破の実情が生々しく描かれている。凄惨な戦闘の中、犠牲になった多くの市民や兵士の遺骨は今でも発掘されるという。この犠牲を強いたナチス政権の無能ぶりは明白だと締めくくるビーヴァーの意見に共感を覚えた。読み応えある一冊。
 戦史だと思って読むと... 戦史だと思って読むと...
タイトルからして戦史に興味を持つ人が手に取るのではないかと思いますが、そういう興味は満たすには少々物足りないのではないかと感じました。ソビエト軍の内情についての記述など興味深いですし、末期戦に興味のある人にとって馴染み深い部隊が登場するのは喜ばしいのですが、どちらかというとツッコミを入れて楽しむ箇所のほうが多いかもしれません。
個人的な感想としては、巻末で解説の人が持ち上げているほど見るべき点は無いように思います。兵器に関する訳注はいい加減で頂けません。訳語も一部ユニークなものがあり、変な意味でおもしろいです。
ボリュームの割には安価だと思いますが内容に見合っているかは評価が分かれるところでしょう。
 小説としては最高なのだが・・・ 小説としては最高なのだが・・・
文章が上手で、地図も見やすい。 大冊ながら一気に通読できる。
だが戦史・外交史としてはいただけない。 4号戦車をしばしばティーガーと誤記したり、FW189偵察機をFW190戦闘爆撃機と混同したりしている。 三大国の秘密会談の場面ではまるでスターリンやチャーチルが著者に本心を打ち明けたかのような記述が見られる。 あくまで小説であって論文ではないのだが、出版前に原稿を専門家に校閲して貰っていればなあと思ってしまう。 それでも読みごたえ十分。 買って損はないと言える。
 イラクの米兵も同じような思い込みの中にいるのではないか? イラクの米兵も同じような思い込みの中にいるのではないか?
赤軍の戦争状態が長引くにつれて、スターリンは「戦地妻」の容認に踏み切ったが、そうした「戦地妻」はドイツ女性へのレイプに対して「わが軍兵士のふるまいは、絶対に正しい」と言い放つ(pp.72-75)。これなんかは、イラクの刑務所で囚人たちを裸にした写真に納まった、アメリカ軍の若い女性兵士を思い出させる。赤軍の兵士たちは「ヨーロッパをファシズムから解放する道徳的使命を引き受けたからには、個人のレベルでも政治のレベルでもまったく思いのままにふるまうことができると」(p.76)思い込んでいたに違いないとしているが、イラクの米兵も同じような思い込みの中にいるのではないか。 ビーヴァーによると、赤軍兵士のドイツ人女性に対するレイプは4つの段階に分けられるという。第一段階は、ドイツに攻め入り、その領内の生活水準の高さを知った赤軍の兵士たちが怒りを燃やして、その怒りの矢を女性に向けていた段階。この段階のレイプには激しい暴力を伴っている。第二段階はやや落ち着いたものの、性的な戦利品として扱った段階。 次の段階はドイツ人女性の側からの接近として考えられる。レイプに暴力が伴わなくなれば、飢餓が進行する中であれば、特に食べさせなければならない子供をかかえている女性は、食物と交換で積極的に春をひさぐ段階だ。第二次大戦期の米軍兵士にレイプが必要なかったのも、大量にタバコや食料を保有していたからだ、としている。この段階でレイプと性的共用の区別はあいまいになり、最終的な第四段階では、「占領地妻」として同棲するようになっていったという(p.607)。
 かつて、そしていまも語られる神々の黄昏 かつて、そしていまも語られる神々の黄昏
ベルリン。かつてはパリすら凌駕すると謳われた都市。その悲劇的な終焉は、ある種の暗い魅力で人の心をざわつかせずにはおきません。
なんとなれば、物書きこそ魅入られるというものではないでしょうか。
ノンフィクション/フィクションを問わず数多くの作家、売文家、劇作家、漫画家、フェミニストらが、この第三帝国帝都の最後の幕間を自らの著作としました。 スターリングラードに関する著作で高い評価を得た著者が、この主題を扱うことになるのも当然の成り行きでしょう。
実際、読みやすく地図も判り易いのですが正直な所、目新しさを感じませんでした。
先にコーネリアス・ライアンによる66年出版の「ヒトラー最後の戦闘」という名著が存在するのですから、何らかのアドバンテージが欲しいところです。もちろん、60年代に知りえなかったソ連側の情報などは興味を引くものではありましたが、この価格を考えると相応だったかは疑問です。とはいえ、「ヒトラー最後の戦闘」は絶版のまま。第三帝国の最終局面を知るのには現在のところもっとも良い本かも知れません。
|
|

[ 単行本 ]
|
赤い楯―ロスチャイルドの謎〈上〉
・広瀬 隆
【集英社】
発売日: 1991-11
参考価格: 2,854 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 750円〜

|
・広瀬 隆
|
カスタマー平均評価:  5 5
 本書を読まずして歴史を語ることなかれ 本書を読まずして歴史を語ることなかれ
かつて、これほど知的興奮を呼び起こし一気に読み込ませた作品はない、全人類必読の書、政治家は本書を読破して行動せよ、メディアに携わる者は読みこなして活動せよ、一般人は熟読して歴史認識を新たにせよ、恐るべき圧倒的5本の矢の権力者たちと、それに張り巡らされた閨閥ネットワーク、彼らによって人類はどこへ向かうのか、彼らによって歴史の真相は連綿と織り込まれてきたのであった、単なるユダヤ陰謀史観と捉えると真実は見えてこない広瀬隆氏の最高作品である
 近代史・現代史の見方が180度変る本 近代史・現代史の見方が180度変る本
実際、この本が出てしばらくして読んだ私は、今まで何も知らなかったのか!と大きな衝撃を受け、それからもう7、8年も経つというのに、このインパクトは衰えない.それは、現在でも、この本で説明できる事件が多いからなのだが.上巻のクライマックスは、やはり第二次世界大戦だろうか.いったい、この戦争は、誰と誰が戦っていたのか!?
|
|

[ 単行本 ]
|
私は貝になりたい―あるBC級戦犯の叫び
・加藤 哲太郎
【春秋社】
発売日: 2005-08
参考価格: 1,680 円(税込み)
販売価格: 1,680 円(税込)
中古価格: 1,000円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・加藤 哲太郎
|
カスタマー平均評価:  5 5
 わたしは戦争反対です。 わたしは戦争反対です。
戦争を知らない世界でうまれました。
生まれてくる魂死んで逝く魂
どこがちがうのでしょうか?
これからの人達は戦争を知らない人のほうが圧倒的に多い。
加藤さんのような作品がベストにはいるということは、うれしいというと
御幣がありますが、大切かとおもいます。
bc級戦犯とはどのような人なのかがよくわかります。
昔映像化されたものを見たようなきがしますが。
とにかくこの作品を戦犯とは戦争とはとつぎつぎにつきさしてゆく
言葉を主人公は貝になりたいと言わしめた、愚かで正直で人間的
標準てき人が刑にしょされるというのは、何回も考えを私達読者に
戦争反対と大きな行動をしなくても、こころに刻みこませることができたの
ではないでしようか。
一読推薦いたします。ぜひ読んでください。
|
|



