|

[ 大型本 ]
|
原寸美術館 画家の手もとに迫る
・結城 昌子
【小学館】
発売日: 2005-05-18
参考価格: 3,990 円(税込み)
販売価格: 3,990 円(税込)
中古価格: 3,100円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・結城 昌子
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 絵の深い理解に 絵の深い理解に
絵のサイズというのは実際に見ると思っていたよりはるかに大きかったり、小さかったりする。これが絵の鑑賞には結構重要だったりする。
この本は小さい絵以外は絵の一部分を原寸で表示しているので、大きさのインパクトを理解するというよりは、技法を良く理解できる。絵の技法というのは日本の美術教育では軽視されているものだけれど、実際には絵を深く理解するには欠くことができないものだ。
たとえば印象派以前の絵が下絵から塗り重ねていくことにより色を作り上げていくことや、印象派が絵の具をダイレクトに塗って効果を出していることが良くわかる。
ボッティチェリが輪郭を描き、ダヴィンチが描いていないことがわかる。このような違いが前期と盛期のルネサンス絵画を分けているということで、ルネサンス絵画への理解も深まる。
あるいはマネが描くガラスの花瓶の驚くべき描写。粗いタッチなのに絵の中では照明で輝く美しい花瓶なのだ。
 細かいことながら 細かいことながら
印刷による表現の限界か、絵の具の盛り上がり具合などは実際に絵を描く人か、見慣れた人でないと、やはりリアルには掴みづらいかも知れません。でも色は綺麗!そこらの画集より、ずっと実際の絵の具の出す鮮やかさに近い色を再現できていると思います。とはいえ、紹介されている作品で実際に私が目にしたのはモローの「雅歌」だけですが(ただし展示してあった場所との光の具合の違いなのか、実物はもう少し深みのある色だったように思います。細かいことですが)。セガンティーニの精細な描写や岸田劉生の麗子像なんかも入ってたら最高でした。これらは次作に期待します。
 マルガリータ王女の衣装! マルガリータ王女の衣装!
とにかくこれは凄い!目から鱗というか大胆でしかもスリリングな試み!
タッチを拡大し絵画全体を無視した潔さに乾杯!
(すいません、興奮しました)
まずはこの本、絵の選定のセンスが素晴らしい!
(というより私好みというべきか)
ヴィーナスの輪郭線、プリマヴェーラの花
牛乳を注ぐ女の壷のふち
そして驚くほど荒いタッチのマルガリータ王女の衣装!
星月夜の息使いが伝わる盛り上がったタッチ!
クリスティーナの体の線の細さ・・・
すべてが発見の連続。ぜひ続編を!
惜しむらくはスケールを知る為のシルエットのセンスがイマイチ?
 普通とはちょっと違う画集 普通とはちょっと違う画集
この本は良いです。
原画の部分的クローズアップ集ですが、クローズアップすることで初めて分かる「絵の味」がひしひしと感じられます。
 余計なことを考えずに作品の細部を見つめるべきなのですが…… 余計なことを考えずに作品の細部を見つめるべきなのですが……
アートエッセイストの著者は、画家の絵筆の動きをもっと感じてほしい、美術史的な知識や文学的なイメージを捨て、細部をたっぷりと見つめてほしい、と本書を企画しました。
本書には西洋名画の全体図をまず紹介したあと、著者が味わってほしいと思う部分を何箇所か原寸大で掲載する、という方法で30人の作品がほぼ一つずつ取り上げられています。
大きな作品でも草花の一本一本までていねいに描かれていることを発見したり、キャンバスの格子模様まで見える作品に画家の絵筆を感じたり、確かにいままでにない絵の見方ができるような気がします。
私が一番衝撃を受けたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』です。壁に絵の具が染み込まず劣化が進んでいる、と知ってはいました。
しかし、単なる“知識”と実際に見るのとは大違い。
原寸大で見ると……、ひどい! こんなにボロボロになっているなんて! という惨状です。同じダ・ヴィンチの『モナ・リザ』にも一面にひび割れが入っているのがはっきり観察され、絵画を後世に伝えることの困難さを感じました。(ちと著者の意図と違うかも?)
かたやミケランジェロがフレスコ技法で描いたシスティーナ礼拝堂の天井画は、20世紀の大修復のおかげか、鮮やかな色彩が細部まで鑑賞できます。映画「ET」にも構図が取り上げられたアダムと創造主が指と指をもう少しで接触させる場面のアップ、もとい、原寸大絵画を見ていると、自分の手の倍くらいの大きさで描かれていることが分りました。天井画だから大きく描いた、ということが納得できます。
たぶん、本書中で一番大きい作品は、ナポレオンとジョゼフィーヌの戴冠式を描いた絵です。621×979cmもある絵をいったい、どこに飾るのやら。ナポレオンの権勢欲の一端を見るような気がします。……が、こういう見かたをすると、また著者に叱られそうですね。
|
|

[ 単行本 ]
|
聖女の条件―万能の聖母マリアと不可能の聖女リタ
・竹下 節子
【中央公論新社】
発売日: 2004-11
参考価格: 2,310 円(税込み)
販売価格: 2,310 円(税込)
中古価格: 1,570円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・竹下 節子
|
カスタマー平均評価:  4 4
 聖人と俗人のあいだ 聖人と俗人のあいだ
ローマに行ったとき、
小さな教会で横の聖母像に小さなろうそくがたくさんともされている
のを見たことがある。
誰でも少しお金を払えば、そのろうそくをたてることができるので、
私もさっそく一本たててきた。本書は、聖母マリアと聖女たちについて解説しながら、
キリスト教の聖人システムの歴史的・現代的な意味を解き明かした好著である。 日本人は「聖人」というと、カタブツでちょっと友達にはなりたくない人という印象をもつのではないだろうか。 しかし、聖母マリアに代表されるキリスト教の聖人たちの物語は
実は弱さや苦しみに満ちた人間たちが織り成す、
私たちにとっての感情移入しやすい奥深さをもったものなのである。 私ははじめて知ったのだが、その一番わかりやすい例が聖女リタという
人物なのである。 くわしい内容は本書を読んでほしいのだが、日本人にも理解しやすい程度にキリスト教についてわかりやすく書かれていて、奇跡や癒し、聖母の出現といった微妙な問題についても優れた考察をおこなっている。 現代におけるフォークロアの重要性も示唆する興味深い一冊である。
 すこーし科学的 すこーし科学的
〜 聖?の腐らない遺体というのを見た事がある。白いつるんとした顔をしていて、人形なのかなあと思っていた。期待していた分、ちょっとしらけた気分であった。
腐らない遺体というのは、カトリック教会で聖人を認定する時の奇跡の一つである。不治の病の癒しというのも、奇跡のひとつである。こんな奇跡をしっかりではなく、すこーし科学してみたのが、〜〜この本である。切り口の面白さは、この作者らしい。
私的には、奇跡をおこそうが、おこさまいが、偉大な事にはかわりはないと思う。〜
|
|

[ 文庫 ]
|
我が名はエリザベス (ちくま文庫)
・入江 曜子
【筑摩書房】
発売日: 2005-10-05
参考価格: 924 円(税込み)
販売価格: 924 円(税込)
中古価格: 99円〜
( 通常24時間以内に発送 )

|
・入江 曜子
|
カスタマー平均評価:  5 5
 美しい文脈で◎です 美しい文脈で◎です
清朝末期から傀儡満州国崩壊まで、史実に則り、皇后婉容を麗しくふくよかに描き出した秀作だと感じた。婉容に焦点をあてた書物が少ないなか、溥儀の内面洞察の側面的役割として本書をセレクトしたが、どうしてなかなか…清朝末期のヨーロッパへ開かれた婉容の聡明さと溥儀への想いと諦めがセツナイ。映画ラストエンペラーでの印象とはまったく違った等身大の女性が浮かび上がる。映画の中で白い蘭を食べるシーン。あのシーンを導入部分にして婉容の生涯を映像化したらこの本。って感じ。はまりました。ただ、、、本当に婉容について…憶測でないのか?どーかは解りません。
|
|

[ 文庫 ]
|
キューバ紀行
・堀田 善衛
【集英社】
発売日: 1995-03
参考価格: 530 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 677円〜

|
・堀田 善衛
|
カスタマー平均評価:  3 3
 カストロとは誰か カストロとは誰か
1966年に岩波書店から出た単行本の文庫化。
カストロがバチスタ政権を倒し、アメリカの支配からキューバを離脱させたのは1959年のことである。それから数年後に現地を訪れた堀田氏が、カストロとその政治について見聞きし、分析したのが本書。
現地のガイドに連れられ、農場や工場を訪ね歩く。カストロ本人とも、ほんの少しだけ会う機会がある。また、カストロの演説などをもとに、彼の政治の内側に迫ろうとしている。
考察そのものは鋭いし、読んでいて面白い。しかし、40年たった現在から見ると、その分析が正しかったのか、いささかの疑問が残る。
熱に浮かされたようにカストロ政権への期待を語る。その若さと勢いを楽しむべきなのかも知れない。
間違っても紀行文ではないので、ご注意。
 「紀行」では終わらない一冊 「紀行」では終わらない一冊
革命数年後のキューバを見た堀田善衛が書いた本作。タイトル通りの紀行文に終わるはずはなく、そこに住む人々や指導者カストロへの感情、キューバという国を通して見たアメリカ中心的世界の歪み等まで、内容は多岐にわたる。対象とは一歩距離を取り、知識人としての姿勢を保とうとしつつも、しかしぐいぐいと引かれていく堀田氏自身の心の動きも感じられて面白い。 今の感覚から見ると言葉も内容も非常に慎重に選びすぎている気もするが、本書が刊行されたのは1966年である。改めて作者の視点の普遍性を感じる。
 キューバに見るアメリカの裏側史 キューバに見るアメリカの裏側史
作家堀田善衛氏が革命後のキューバを訪れ、「アメリカ経由の新聞記事」でなく、現地の空気に直接触れた印象を綴った旅行記。アメリカの資本あるいは政治的思惑に翻弄されてきたキューバに、「人間としてまともな生活」(p.58)を取り戻す対抗運動として、革命家フィデロ・カストロが現れたこと、革命が隆起してきたことなど、革命に至る経緯を作家の目で観察している。この本の特徴は、近代キューバ史を描写が、同時に、北方の強大国アメリカの政治的・経済的な支配構造の描写、アメリカの思惑に小さなキューバがどれほど翻弄されてしまったのかの描写となっている点にある。この点、アメリカを考えるにも興味深い考察となっている。 ただ気になる点を挙げるとするならば、キューバ人へ接近する姿勢が今ひとつ踏み込めていないような気がする。例えば、苦しみの歴史を生き抜かなければならなかったお婆さんに、歴史から受けなければならなかった悲しみの本質を尋ねようと考えるも、お婆さんが「通りすがりの一夜の旅の者には、たとい話して聞かせても、この気持ちはわからぬということを、知っていたのではないまでも感じていた」(p.207)のであろうと推測するばかりで、堀田氏は敢えて問いかけようとしていない。 良識的な作家として、悲しみの領域にズケズケと入り込まない姿勢を保っているかも知れないが、良識を伴うことでキューバ人により深く共感するができるだろうし、もう一つ踏み込むことで著者のキューバ観もより深められたであろうと思う。そんな風に考えられるだけに、何とも残念なのである。
|
|

[ 単行本 ]
|
暦をつくった人々―人類は正確な一年をどう決めてきたか
・デイヴィッド・E. ダンカン
【河出書房新社】
発売日: 1998-12
参考価格: 2,415 円(税込み)
販売価格: 2,415 円(税込)
中古価格: 1,199円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・デイヴィッド・E. ダンカン
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 旧石器人のカレンダー 旧石器人のカレンダー
1年が365日で、それが12個の月からなっているのはなぜか?
その1ヶ月が30日だったり31日だったり28日だったりするのはなぜか?
私たちはカレンダーを当たり前に使っているが、よく考えれば不思議なことだらけだ。
人間は「考える」ということを、簡単にやめられるのである。
考えることをやめてしまった中世暗黒時代は、文字通りの深い闇に包まれている。
最近の様子を良く知らないが、日本の学校ではいまだに円周率は「3」である、
などと教えているのだろうか。
だとすれば、そんな国の人が、暗黒時代の迷信をわらえるだろうか。
読んでいるうちに、暦を考えることは、学問の基礎の重要な1つであるような気がしてきた。
旧石器時代のカレンダー?と目される遺物については、ぜひ本書の仮説を読んでいただきたい。
 宗教が暦の科学を発展させた 宗教が暦の科学を発展させた
この本書を読むまで、宗教がそれほどまでに時間と暦に深く関わっているとは知りませんでした。時間の概念も、中世の農民と、時計とスケジュール帳に追い立てられている私たちでは、まったく異なるものでしょう。この本は、人間と時間、暦の関わり合いを、宗教を巧みに絡ませて、私たちに教えてくれます。ただ、明確なストーリーがないですから、最後まで読み通すのには時間がかかるかもしれません。ですが、必ずや知的好奇心を満たしてくれるでしょう。本書には参考文献の一覧も掲載されており、さらに深く暦と人間の関わりを追うことも可能です。暦と人間の関わりに興味のある人は、本棚に一冊置いておくと重宝すると思います。
|
|

[ 単行本 ]
|
ヴァチカン―ローマ法王、祈りの時
・野町 和嘉 ・南里 空海
【世界文化社】
発売日: 2000-06
参考価格: 2,940 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 1,124円〜

|
・野町 和嘉
・南里 空海
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 最高のヴァチカン紹介 最高のヴァチカン紹介
中を開いてみると、大変美しい写真の数々にまず圧倒されます。
正直少し価格が高いので最初は購入を見合わせていたのですが、
書店でパラパラめくってみて、すぐにネットで注文を出しました。
これないら三千円近い価格でも買う価値があります。そして、ゆっくり読んで行きますと、著者がカトリックの信者でなく、
すごく客観的に書かれているのが新鮮です。
何故かと言うと、カトリックの信者や聖職者が書くと
どうしても、著者の信仰基準が影響してきて、内容が偏るからです。 特に、前教皇ヨハネ・パウロ2世の紹介文はすごく素直で良いです。
これなら、宗教に興味がない人が見ても違和感なく読めるでしょう。
もちろん信者さんにも手に入れて欲しい一冊です。
 美と祈り 美と祈り
蒼を基調にした金色の帯がついている美しい本です。
清々しい美しさと言うか、聖なる美しさと言うか、写真も文章も美しい。この本を見つけたのが、ちょうどヨハネ・パウロ二世が危篤状態のときでした。値段も手軽に買えなかったので、書店で読んでいたのですが、ヨハネ・パウロ二世になるまでの経歴がとても詳しく書いてあり、非常に参考になりました。読み終わらないうちにヨハネ・パウロ二世は天に召され、記念にと買い求めました。次の日からその書店にその本が山積みになっていたのには苦笑しましたが。しかし、ヴァチカンの組織、また美術、そして豊富な写真・・・・どれも読み応え見ごたえ十分です。新法王が誕生した今、この本を読んでカトリックとは何か、ヨハネ・パウロ二世とはどんな人物だったのか知ることは意義あることだと思います。 南里氏があとがきに「ヨハネ・パウロ二世をカリスマ化していると思われる読者がおられたら、それはひとえに著者が法王に魅せられたゆえの責任である」と書いてあることも非常に潔く共感がもてました。
 写真が綺麗 写真が綺麗
新千年紀のために1000年間閉じられていた「大聖年の扉」が1999年12月24日にヨハネ・パウロ二世の手で開かれました。
三千年紀を迎えるローマ法王ヨハネ・パウロ二世の祈りを綺麗な写真と文で紹介しています。
信者でなくても神聖が気持ちになります。
ヴァチカンに行った人、これから行く人に是非読んでほしい本です!
|
|

[ 単行本 ]
|
公営競技の文化経済学 (文化経済学ライブラリー)
・佐々木 晃彦
【芙蓉書房出版】
発売日: 1999-03
参考価格: 1,575 円(税込み)
販売価格: 1,575 円(税込)
( 通常3〜5週間以内に発送 )


|
・佐々木 晃彦
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
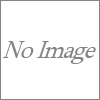
[ 単行本 ]
|
「坂の上の雲」では分からない旅順攻防戦―乃木司令部は無能ではなかった
・兵頭 二十八 ・別宮 暖朗
【並木書房】
発売日: 2004-03
参考価格: 1,890 円(税込み)
販売価格: 1,890 円(税込)
中古価格: 500円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・兵頭 二十八
・別宮 暖朗
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 別宮さんありがとう 別宮さんありがとう
20代前半に初めて「坂の上」を読んだときには、ただただ感動しました。しかし40になろうとして、また、すこしはメディアや社会の組織というものを見て、「坂の上」に不自然と思えるところが多々出てきました。そもそも、絵に描いたような無能者とか大天才とか、そうはいないと思います。本書のおかげで、いろいろとおかしい理由を具体的に確認できたと思います。たとえば「坂の上」の記述からは、読者は要塞についてダムのようなイメージをうけて不思議はないのですが、実際はそうでなかったなど。塩野七生氏は地図とか絵とかでの具体化がお好きですが、そういう作業を司馬遼太郎氏は余りやらなかったのかなと思います。
 司馬遼太郎批判よりも・・・ 司馬遼太郎批判よりも・・・
改めて言うまでもないことではありますが、「坂の上の雲」は小説で
あり、ノンフィクションではありません。司馬氏がエッセイなどで自
身の歴史観を元にさまざま考えを述べていたことは確かですが、所詮
小説家というのはストーリーが元にあって「そうあって欲しい」とい
うバイアスをかけて史料を読むので、その見解を事実ととらえてはい
けません。
・・・と念のため前置きしておいて、この本の真価は、要塞戦、塹壕
戦の実態を旅順攻防戦を教材に読者にわかりやすく教えてくれるとこ
ろにあります。(司馬遼太郎批判はそれほどはでてこない)
初めに塹壕戦の技術的ポイントを教えてくれ、次に時系列で旅順攻防
戦の双方の駆け引きが描かれます。原則は原則、しかし、個々の戦場
ではさまざまな要素があり、かならずしもセオリーどおりにはいきま
せん。
例えば、旅順では港内の艦隊の存在がキーになっていたが、それをめ
ぐって海軍と陸軍の間に対立があり、それが現場での判断を拘束して
いたこと。一方のロシア側もセオリーどおりの篭城を厳命するステッ
セルに対し、出撃を主張し、陣頭に立つコンドラチェンコの方が戦術
的には誤っていたにもかかわらず兵士には人気があったという矛盾を
抱えていました。そして、勝敗を決したのは、陣地をどれくらい奪う
かではなく、人命をどれだけ奪うかでした。これに決定的役割を果た
したのは、28サンチ砲でありそれを推進したのはある技術将校でし
た・・・
こういった内包されたドラマが読者に知的興奮を与えながら、軍事的
知識皆無である私たち日本人に塹壕戦の知識も与えてくれます。
この時代の知識を現代にそのまま援用することは無理がありますが、
例えば、イラク戦争でイラク軍があれほどあっさりと降伏してしまっ
たことの原因を考察する上でのヒントになるかもしれません。
なお、著者はもともとの専門家ではなく前歴がサラリーマンという方
ですが、文体はわかりやすいし、構成もしっかりしているので、その
点での心配はいりません。
 乃木は無能だったのか…ついでに要塞築城学べます! 乃木は無能だったのか…ついでに要塞築城学べます!
旅順攻略戦における第3軍(乃木)司令部の作戦・戦術が実は正鵠を得たものであった…と言う説は、かなり前−司馬遼太郎氏存命時−に、確か…永井氏が“現代と戦略”(あるいは児島襄氏の著作(タイトル失念…)だったか?)と言う著作で述べていた記憶がありますが、この書も乃木と参謀連が正しかったのではないか?を詳細に論じています。
203高地占領の価値はどうだったのか?司馬氏が“坂の上…”で採用した資料は偏向していなかったか?海軍の怠惰・横暴は如何?日露戦役後の意図的な乃木司令部への中傷はどのようなものだったか?ある技術将校の類い希なる功績は?……などなど刮目(?)すべき事項が並べられています。
なお、旅順要塞にちなんで、欧州を中心とした築城・攻城戦の歴史も詳述されていますので、興味ある方には必携かもしれません。
 乃木の評価で日本人が問われている 乃木の評価で日本人が問われている
今の日本人に真に必要なのは、『坂の上の雲』よりも、本書や福田和也氏の『乃木希典』ではないでしょうか。
かつて私も『坂の上の雲』を貪るように読みました。
それほど、司馬氏の筆致はエキサイティングで、歴史とはこんなに面白いものなのか、と、その後の人生の一部を決定付けた気がします。高度成長期の日本人にとって、『坂の上の雲』のような物語が必要であったように、自分の人生のある時期には『坂の上の雲』が養分になった訳です。 乃木という、能力に様々な限界があり、そのことを強く自覚しながらも懸命に闘った男を、単なる浪花節ではなく、現代人がどのように評価するかが、成長に限界の見えた日本の、日本人に問われている大きな課題なのではないでしょうか。
 最近いなくなった真面目な研究者 最近いなくなった真面目な研究者
別宮暖朗は最近日本にいなくなった真面目な研究者です。
他言論人が語る日露戦争と比較してみてください。もはや他言論人
を「超えて」しまってます。
例えば「第2章 歩兵の突撃だけが要塞を落とせる」「第3章 要塞は攻略されねばならない」を読んでください。私などは『坂の上の雲』で学んだ日露戦争観が木っ端微塵に吹き飛びました。 日露戦史ファンには当然お勧めですが、「本を書くという作業はここまで調べねばならぬのか!」といった刺激が必要な手抜き言論人にも読んで頂きたい一冊です。
|
|

[ 単行本 ]
|
ビンゲンのヒルデガルトの世界
・種村 季弘
【青土社】
発売日: 2002-07
参考価格: 2,940 円(税込み)
販売価格: 2,940 円(税込)
中古価格: 2,450円〜
( 通常24時間以内に発送 )


|
・種村 季弘
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
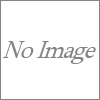
[ 単行本 ]
|
NHK 電子立国日本の自叙伝〈完結〉
・相田 洋
【日本放送出版協会】
発売日: 1992-05
参考価格: 1,529 円(税込み)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 259円〜

|
・相田 洋
|
カスタマー平均評価: 0
|
|



