|
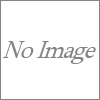
[ ���� ]
|
��팂�ĉ��\��픪�N�̋L�^ (���l��NF����)
�E��{ �O�O
�y���l�Ёz
�������F 1994-05
�Q�l���i�F 840 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 840 �~�i�ō��j
�����i�F 365�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E��{ �O�O
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4.5 4.5
 ��_�Ɉ����ꂽ�j ��_�Ɉ����ꂽ�j
���{�C�R�g�b�v�̌��ĉ��B
�ނ̒W�X�Ƃ�����j�̒��ɁB
�킢�����퉻���Ă��錻�������A
�܂��A�j�̓����{�\���݂�B
���s�s�ȌR���̒��ŁA
����t�����ɗ^����ꂽ�C�����ʂ������A
���m���̋L�^�B
�ނ̋L�^�������Đ��Q�O�Q�@�́A
�j�������ł���B
�����M���Ȃ��āA�Ȃɂ�M���悤���B
���{�̓�����͑�ϗD�G�������B
���̒����푈�̒��ŁA
�O���ɗ����Ȃ���A�����c��������
���Đ��Q�O�Q�@�́A�����m�푈��ł���B
���̒����푈��
���ĉ��Ƃ��Đ����c�����B
���ꂾ���ł��A�f���炵���B
��_�ɍł������ꂽ��퓋����ł���B
���l�ЕҏW��������ƂȂ��Ɗ����Ă���̂ŁA
���͂S�B
���ݓ��荢����A
��팂�ĉ��\��픪�N�̉��
������Ȃ琯�T�B
�V���̘Q�l�ՓO�B
�ނ͎����Q�l�ƕ]���Ă���B
���{�̊C�R�̒��ŁA
������Q�l�Ɗ����Ă����ނ��B
�������Ĉ������B
 ���Đ�202�@�ɋU��Ȃ��I�I ���Đ�202�@�ɋU��Ȃ��I�I
�����A�^��p�A�A�[�����[�V�����A���o�E���A�g���b�N�A�t�B���s���A����B
��{�͏�ɐ��ɂ����B
���Đ��������̂͂��̑�����籌���ɂ����̂����炾�B���ʂ̓G��100�@200�@�ƈ���ɉ���������ɗ���B
�G�̐��������Đ��������Ă����B
���O�Y�̑��̃T�����C�ƈႤ�R�[�X�����ł���̂��ǂމ��l�̂���Ƃ��낾�B
��䂪�J�펞����t�B���s�����U�������̂ɑ��A��{�͐^��p�A�X��C�C���Ƌ�����������B
���̓K�_���J�i���ł̏o���ŕ��������{�A�������̂ɑ��A��{�͓��{���ꂵ���Ƃ�����ɑ����Ő킢�����Ă����B
18�N�ɂ͂��łɂ��������Ă���B
�u�����N�̖ڂɂ����s�͖��炩�������B��X�͂����ڋ��҂ɂȂ肽���Ȃ����߂ɐ���Ă����B���ꂪ���o�E�������B�v
�����ł͂���Ȃ�o���N���ӂ��ēG�͂ɑ̓����肷����U����������V�[�������x�ƂȂ��`����Ă���B�ǂ�ȋC�����Ō������Ă����̂��낤�B
 ��팂�ĉ��@��픪�N�̋L�^ ��팂�ĉ��@��픪�N�̋L�^
��Ò����ɂ��ėE�҉ʊ��@�D�ꂽ���f�@�������������������@��̓��X��W�X�Ə����Ă����邪�@���݂̎��B�������Ă��鐶����
�ł͑z�������Ȃ����X�������Ă���ꂽ���Ƃ͊���������ł�
���͐풆�Ƃ͈Ⴄ�킢�̓��X�������Ǝv���܂����Ⴍ���ĖS���Ȃ�ꂽ���͎c�O�ł��@��{���̐��̘b��L���Ȃǂ������ƌ�������������
 ��{�t�@���K�� ��{�t�@���K��
��{���̐퓬�L�^��ǂ�ŁA�����[���͎̂��̂Q�_�ł���B���ɁA��p��ŏ��s�����܂�Ƃ������ƁB�G���ǂ̈ʒu���炠����邩�A�ǂ�ȋ@�킪������邩�A�ǂ��܂Ő[�ǂ����Ă悢���A�Ƃ������Ƃ��A��{���́A�����炭�V�˂ƌo���Œm���Ă����̂ł���B
���̖{�ɂ͏����ĂȂ����A��{���̎��͂͂P�E�O���炢�������Ƃ�����B�������A�G�@�̔����͑��������Ƃ����̂́A�ǂ�ł�������Ȃ̂��B���l�̂��Ƃ́A���O�Y�����w�E���Ă���B ���ɁA�W�c�s���ł͎w�����̔\�͂őS���̉^�������܂邱�ƁB�o���̐w�����ɗ�����ꂽ�����͑S�łɋ߂�����A�t�ɂ����ꂽ��p����������w������������ƁA�����̑��Q�͏��Ȃ��A��ʂ��オ��B
���̂�����͌���̑g�D�ɂ��ʂ�����̂����邾�낤�B
�Ƃ��ɐ푈�ł́A�l�̐����Ƃ����`�ŁA�͂����肻�ꂪ�������̂ŁA�����낵���B ���̂̕ω��������[���B��������ł́A���x�������Ėq��̋������ǂ������肵�ėV��ł������A�X��C�C��ł��A����l�߂����ɂ����l�Ƃ��ď[�����Ă������Ƃ��f����B
�K�����Ƃ����̂��A�X��C�C��̋A������ł���B�X��C�C��ŁA��{���́A���߂Ĉ���Ŗ���������������̂��o�������_����B�����ē��n�ɂ��ǂ��ă~�b�h�E�F�C�̔s���m��B
��������́A�ǂ�ł��Ă��A���炢�炵�Ă���̂��悭�`����Ă���B
�J�평���̂悤�ȏ[�����͉e���Ђ��߁A���܂肭��G�ɂƂɂ������ɂ������������Ă���A�Ƃ�����ۂł���B
�v����ɁA�X��C�A�~�b�h�E�F�C����������ɁA��{���̈ӎ�����A�푈�ւ̏����A�Ƃ����ڕW�������Ă����̂ł���B
���o�E���h�����{���̃n�C���C�g�̂ЂƂ����A����ƂĂ��A�����ւ̈���Ƃ�������Ő���Ă����̂ł͂Ȃ��B�ǂ�������Ȃ��悤�Ɏx���Ă���A�Ƃ�����ۂ����B
�d��������l�ԂƂ��āA���������͂炢���̂����������낤�B ���U�ɂ��Ă��A�Z������ۓI�ȋL�q������B���U���m��n��ƑS�R�̎m�C�͖ڂɌ����ė������A�Ƃ������̂ł���B
��{���̂悤�ȗ��̃p�C���b�g�ɂȂ�ƁA���_�_�͂Ƃ������A��p�Ƃ��Ă̓��U�U���̖��Ӗ������A�����̑O���̏���A���݂��݂ƌ���Ă����̂ł��낤�B
 ���{�C�R�q����̎��� ���{�C�R�q����̎���
���ċ@���Q�O�Q�@�I�`���̃g�b�v�G�[�X�A���{�C�R�q����̎������₵�����ċL�^�B���{�ō��̌��ċL�^�����A��{�O�O�@���C�R���сi�R�S�������j�̖L�x�Ȏ���o���A���Ă̐^���������L������z�^�B
�{��i�͊�{�������\�������ŏ����ꂽ��z�^�ł��������A
���a�R�O�N�ɕa������Ĉȗ��A���w�l�̂��Ƃɕۊǂ���A���̖ڂ����鎖�̂Ȃ������ނ̈�e�ł���B�܂��ɊC�R������{�̎���ł�������{���̈�e��ǂ܂����āA���͌��Ȃ��ł��傤�B
�ǂ��炩�Ƃ����Ɖ��Č^�ł���ꌂ���E��@���ɈӂƂ���B
�b��i�������Ĕw�����肠���킢�j�͍ŏI��i�Ƃ���̂��A���ĉ��ɋ��ʂ���킢���Ƃ����悤�B�������ނ́A�����o�g�̕���������ɂ��ւ�炸�A�������߂Ă����̂ł���B��������s�����Ă����Ƃ͂����A�ނɑ���R�̂悹����҂̑傫�����f����B�܂��ɓ��ʑҋ��ƌ�����B
�܂��A�O�����e�i����e�j�̑��l�҂ł����{���̓��e���@�Ȃǂ�������Ă���A���ɋ����[���B�ނ̕��͎͂��M�ɖ������A�����ɂ߂��j�̂�����������C�T�I�ȕ��͋C����������B
�܂����@�ɕ`���u���v�̌��ă}�[�N�i��^�@�͔��d���j�Ɍւ�������Ă���ꂽ�悤�ŁA�����ɂ������Γo�ꂷ��B�����������U�O�ȏ�������̈��@�́A���n�ɑ����č������ە�����ׂɓW�����ꂽ�̂��������B��y�������A���̖����ɂ��錂�ă}�[�N�ɓ���A�ؕ|�����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�G�@��253-102���@�ɂ͈�ڒu���Ă����ɈႢ�Ȃ��B��ɍőO���ɂ����āA�I��܂Ŋ��������Ȃ��p�Y�̈�e��ǂ�ŗ~�����B
|
|

[ �P�s�{ ]
|
�s�k��������߂� �� ����Ł\�����̓��{�l
�E�W���� �_���[
�y��g���X�z
�������F 2004-02
�Q�l���i�F 2,730 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 2,730 �~�i�ō��j
�����i�F 2,100�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )


|
�E�W���� �_���[
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 5 5
 ���{�l�̖����`�̈�̏o���_������ ���{�l�̖����`�̈�̏o���_������
�ォ��̖����`�Ƃ͉��������̂��Ƃ������Ƃ��l����������B���U�O�N�������a�̏I����������A���̎����ɉ����ꂽ�l�X�Ȍ���̉e�����Ő����Ă��邱�Ƃ��v�킹��B�������A���̎����m��Ȃ����̂ɂƂ��ẮA��͂肻����O���猤�������A�����J�l�̘_�l�͂ƂĂ��ǂ݂₷���B���̓ǂ݂₷���̈Ӗ����l�����ŁA���������l�̕��͂������ɓǂނׂ���������Ȃ��B
 ���ɂȂ�܂��� ���ɂȂ�܂���
���ɂȂ�܂����B�S�Ă̓��{�l�͓ǂނׂ��ł���B���Ƃ��x����Ȃ����߂ɂˁB
�펞���ɍ��̂����я����ɋ]���������Ă����푈�w���ҒB���A�푈�ɕ������r�[�A
�؋����ނ̏��p��R�������̉������ɖ�N�ɂȂ��Ă���p����ۓI�������B��������
�������S�l�̉쎀�҂��o�Ă���̂ɔނ�͎������₷�̂Ɍ����������B
����́A�����݁A�G���[�g�w�̂���Ă��邱�ƂƓ�������Ȃ����Ǝv���B
���̂����ԑ���Ɂu���������v������ł���ԂɁA�w���ґw�B�͐ŋ��̂����܂�����
���Ď������₵�Ă���Ƃ����\�}�ł���B
����������͈̂�ʏ����ł���B���j����w�Ԃ��Ƃ̏d�v�����A���̖{�͋����Ă��ꂽ�B
�u���j�͌J��Ԃ��v�Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�B���{���Ƃ��x���ꂽ���Ȃ��l��
�ǂނׂ����B
 ���ʂ̐l�X�̕��� ���ʂ̐l�X�̕���
�č��ɂ�������{�j�����̑�ƁA�W�����E�_���[���������{���w�s�k��������߂āx�́A�s�킩��T���t�����V�X�R�u�a�Ɏ����̉��̓��{��7�N�Ԃ������ƕ`���o�����̂ł���B��̌R�ɂ����v�͏��҂ɂ��u�����t���v�ł������Ƃ��A���̎Y���ł����㖯���`�ɑ��Ĕے�I�ȃX�^���X����錾���͍��Ȃ��������B�������Ȃ��璘�҂́A�u�����t���v�̍\�������������Ǝ��͍̂m�肵���A�������s�҂̑�������I�ɎI�ȑ��݂ł������Ƃ݂邱�Ƃ����₷��B�P�Ɂu���҂��s�҂ɉ����������v�ł͂Ȃ��A���{��̂��u���i�v�Ƃ��đ����A�s�҂����҂ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��ɒ��ڂ���̂ł���B
���̂悤�Ȗ��ӎ��̉��ɁA���҂́A��̊����{�̎Љ�E�����ɏœ_�āA�u���O�ӎ��v���d����낤�Ƃ���B�u���I�ƂȂ������E�ɂ����āA�Љ�̑S�Ă̊K�w�̐l�X�̐������A�S�Ă���蒼���Ƃ������ƁA���ꂪ�ǂ�Ȃ��Ƃ��Ӗ���������������낤�Ɠw�͂����v�iP9�j�Ƃ����̂ł���B
����Ȗ{���́A�܂��ɓ��{�́u�Љ�̑S�Ă̊K�w�̐l�X�v���A�s����ǂ��}���A���̐푈���ǂ��F�����A��̌R�Ƃ��̉��v�ɂǂ����������A���a�Ɩ����`�ɂ��Ăǂ��l��������`���o���u�s�k�̕���v�ł���B�㊪�ł́A���̐푈�̂����炵���j��Ɛ�]�A���E������������Ƃ��邩�̂悤�ɓo�ꂵ�Ă����V���������A������GHQ�̉��v�Ƃ���ɑ��閯�O�̌ĉ����`�����B�u��ヌ�W�[���v����̒E�p������鍡�A�����������{�́u���v�Ƃ͉��������̂����l��������Ŗ{���͔����Ă͒ʂ�Ȃ�����ł��낤�B�����{�́u���ʂ̐l�X�v�̐����l��`�������̃h���}�e�B�b�N�ȁu����v����������Ɩ��킢�����B
 �P���͂�����A�������̔@�� �P���͂�����A�������̔@��
�㊪�͎R�c�����Y������͑��Y�̖{�ȂǂŊ��ɒm���Ă������Ƃ������A���܂�C���p�N�g���Ȃ������B�풆�h�̐l�X�ɂ͏��X�����ł��낤�B�������҂̈Ӑ}�Ƃ��ẮA���肩���������悤�ɁA�p���p���F�ČR�l���}�b�J�[�T�[�F���a�V�c�Ƃ����|���}����o�����������킯�ŁA���{�łł����̕����͍\����O���Ȃ������̂�������Ȃ��B�����̃t�F���[�Y�y���Ȃ�l�����o�ꂵ�Ă���A��R�����[���Ȃ�B
 ���{�l���G�ꂽ���Ȃ������ӎ��������Ȃ������H ���{�l���G�ꂽ���Ȃ������ӎ��������Ȃ������H
���܂���ˎ����̐푈����̍������̖����ǂ�ł������Ƃ��������A�ώ@�Ҏ��_�Ɠ����Ҏ��_�ł͂ǂ����Ⴄ�悤���B��ˎ����̖���ł́A���̖{�Ɠ����悤�ɐ푈����̊J�����Ɠ����ɁA���̖{�ł͏�����Ă��Ȃ����Ċ���A���Ċ�������B���炭�ꎟ������V������������ɗ����Ă��邩�炩������Ȃ��B���̖{�ɂ͓����̐����Ɋւ���C���^�r���[����؏o�Ă��Ȃ��B�V�����C���^�r���[�������̂��g���Ă��邾���ł���B
���@�_��A���Ȃ���͂��邪�A���{�l���G�ꂽ���Ȃ������ɂ��ď����Ă���_�ŕ]���ł���B
|
|

[ �P�s�{ ]
|
�s�k��������߂� �� ����Ł\�����̓��{�l
�E�W���� �_���[
�y��g���X�z
�������F 2004-02
�Q�l���i�F 2,730 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 2,730 �~�i�ō��j
�����i�F 1,900�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )


|
�E�W���� �_���[
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4 4
 ���{�́u���v�̌��_ ���{�́u���v�̌��_
�č��ɂ�������{�j�����̑�ƁA�W�����E�_���[���������{���w�s�k��������߂āx�́A�s�킩��T���t�����V�X�R�u�a�Ɏ����̉��̓��{��7�N�Ԃ������ƕ`���o�����̂ł���B��̌R�ɂ����v�͏��҂ɂ��u�����t���v�ł������Ƃ��A���̎Y���ł����㖯���`�ɑ��Ĕے�I�ȃX�^���X����錾���͍��Ȃ��������B�������Ȃ��璘�҂́A�u�����t���v�̍\�������������Ǝ��͍̂m�肵���A�������s�҂̑�������I�ɎI�ȑ��݂ł������Ƃ݂邱�Ƃ����₷��B�P�Ɂu���҂��s�҂ɉ����������v�ł͂Ȃ��A���{��̂��u���i�v�Ƃ��đ����A�s�҂����҂ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��ɒ��ڂ���̂ł���B
�����ł͓V�c�́u�l�Ԑ錾�v�A�V���@����A�����ٔ����`����A�s�҂�����{�̕ێ�w���w���u�ォ��̊v���v��ώ������A���́u�V�c�������`�v��z���グ�Ă����ߒ����`�����B����ɁA���{�̌o�ϐ������x���邱�ƂɂȂ�A���č����ᔻ���Ă�܂Ȃ����{�̊�����`�I���{��`�ɂ��Ă��A���͂��ꂪ��̊��ɂ�����u���č���v�̈�Y���Ƃ������Ƃ��_�����Ă���B
�u��ヌ�W�[���v����̒E�p������鍡�A�����������{�́u���v�Ƃ͉��������̂����l��������Ŗ{���͔����Ă͒ʂ�Ȃ�����ł��낤�B
�u���{�͂ǂ�����A�����Ɏc�s�Ȕj��������炷�\�͂�Ɨ͂Ŏ����ƂȂ��A���E�̍��X�␢�E�̐l�X����܂��߂Ɍ��������Ă��炦�鍑�ɂȂ��̂��H�v�i��P427�j
��H�ɗ����A�_���[�̂��̖₢�����͏d���B
 �u�b�V���̒������剻���z��č��l�ɐM���������{ �u�b�V���̒������剻���z��č��l�ɐM���������{
�_���[�ɂ���45�N���@�̓}�b�J�[�T�[��������I�[�X�g�����A����V�c�����ׁA���̂悤�ȋK��ɂ����Ƃ����B�܂��V�c���쎝���n�[���D���̃t�F���[�Y�Ƃ�����R�l�̎v�z�̉e�����傫�������ƁB�ǂ����M�����Ȃ��B�V�c�����ǂ����邩�Ƃ������d�厖���͑哝�̂��͂��ߖ{���̂����Ə�̃��x���Ō��肳��Ă����͂����B���S�ɕ��͐��������}�b�J�[�T�[�i�ߕ������{�l�́u�Q������v�⋤�Y��`�̐Z����{�C�ŋ��ꂽ�Ƃ��v���Ȃ��B��͂�V�c�l����킪�t�����ĕč��̍��v�Nj��ɓO������̂����������̂��B�������ʓI�ɓ��{�����@�͊m���ɏ��{�ĂȂǂ��ǂ��Ƃ���̂�����̂ɂȂ����Ƃ͎v���B�܂��_�i�ے���ǂ������B�ł��č����ǂ����̍��ɐ�̂����́u�l�Ԑ錾�v����������Ă��]���Ƃ͎v���Ȃ��B�S�������ʗǂ����ƂȂ̂���.........�B�i��͂莛��͋ȎҁB�j
 ��肽������ ��肽������
�㊪�Ƃ͈Ⴂ�����́A��̐���̊j�ƂȂ镔���̘b�ł���B��́A�푈�ƍߐl����ѓ����ٔ��̘b�ł���B������́A�A�����J�R�ɂ��v�z�����̘b�ł���B�v�͌��{�ł���B
���{�Ɏ��R�Ɩ����`��A���t����Ƃ������ڂŁA�v�z�������s���A�m�b�̂�����̂��ٔ��ɑ���A��肽������ł���B�v�z�������Ȃ킿���{�́AGHQ�̍\�����l�̃X�L�����_�����܂ߖ��_���ێ����邽�߂̂��̂���A�����Y��`�̖h�g��̂��߂̍��ƂÂ��莊��܂ł���Ƃ�����ꍇ�ōs���Ă���B�������A�m�łƂ����������킯�ł��Ȃ��A�ނ���s�������������ŁA���҂ɂ��s�҂����߈ȊO�̉����ł��Ȃ��悤�ɂ����v���Ȃ��B���ɓ����ٔ��͂Ђǂ����̂ł���B�������N�Ԃ͉čP��̃e���r�œ����ٔ������グ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������́A���x�������o�����炻�̍����͂悭�킩���Ă���B���������A�ق�����ɂ��锻���́A�p�Ė@�̒m���ǂ��납�A���ۂ̍��ۍٔ��Ɋւ���m���������Ȃ��l�Ԃ����ō\������Ă���B�܂��ɃA�����J����уC�M���X�̑���l�`�ɂ��������Ȃ��B�n�������̔����������Ȃ܂ł̖����ł���B�哌���푈�𐳓�������C�͂Ȃ����A�ނ͂����܂ł����҂��s�҂����������߂̂��̂ł������肦�Ȃ��B
���̂悤�ȏ���A�v�z�����́A�A�t�K�j�X�^����C���N�ł��s���Ă��邱�Ƃł��낤�B���{�̐�̉��́A���͐��10���N�ɂ킽��킢�ʂ��Ă������߂ɁA���_�I�ɂ����̓I�ɂ��K�����Ă������߂ɔ�r�I�ȒP�ɓ��������܂��������̂ł��낤�B�������A���{�l�̎��R�ӎv���o�̂Ȃ��⏟���n�ɏ��Ƃ����Ɠ��̎v�l���������Ă��邾�낤���B�A�����J�l��C�M���X�l�̂��̂悤�Ȋ��o�ł̊C�O�ł̓W�J�́A�����ĕ��a�������炷���̂ł͂Ȃ������݂������邾���̂��̂ł��낤�B
���̖{�́A�㊪�Ƃ̃J�X�Ƃ蕶���̂悤�ȑ�O�����̘b�����A�����I�v�z�����̘b�ł���A�����̕������Ȃ�̉��l�����Ǝv����B
 �A���n�ى�{�Ȃ�Ȃ��H �A���n�ى�{�Ȃ�Ȃ��H
�ŏ��ɓǂ��͈��|�I�Ȏ������Y��Ȍ��t�Ŋ���������ꂽ���悭�悭�l���Ă݂�ƃA�����J�͊J���R�ƌ}�����ăA�����J�̍�����V���@�͌��Ǘǂ������B���{�̃A�����J���͐����������Ƃ��������{�Ȃ�Ȃ����Ǝv�����B�����v������Ԃ̗��R�͕ĉp���U���������R�����l�����ꓖ����I�ɍU�������Ɛ�������Ă�����ł��B�������{���͐��������̌o�ϕ����ɒǂ��l�߂��Đ؉H�l���Ă₯�����ɂȂ��Đ푈�����̂��^���������͂��ł��B�ٔ��̔��N�l�ł���A�����J���d�|���l�����炱�̍ٔ��U�P���ƌ������̂��p�������̎�Ȏ咣�������͂��ł��B�ŋ߂̓��{�̖v���̓A�����J�̐V����œ��{�l���o�J�ɂȂ������炾�Ǝv���B������v�v�Q�Ō��l�����ꂠ����I�ɍU�������Ɛ������č���̖v��������Ɠ������Ƃ��Ɛ�������_���[�̐������ɋ^��Ɋ����܂��B
���ɂ�������ȐA���n�ى�{���Ǝv��
 �������j �������j
�{����ǂƂ��ɁA������a�������������~�܂��Ă��܂��̂́A�������j(oral history)�ƌ��I���j�̍��Ȃ̂�������Ȃ��B���j�̎��Ԃŋ���������j�ȊO�ɁA���������͂ސl����������œ`����ꂽ���j�����邩�炩������Ȃ��B����́A�R���̑��ł���A�풆�̃v���p�K���_�ł���A�Ŏs�ł���A���Y��`�̑䓪�ł���A�V�c���������ɓ��{�̗��j�ɂ����ċ@�\���Ă������Ƃ������Ƃł���B����ł��A���Ɍ������j��`���Ă��ꂽ�l�X�́A�ߎS�ȗ��j�̒��ł��������т邽�߂ɂ��̐l���������������m�b�ƁA�����̍��ƍ��̗��j�Ɍւ�������Ƃ̑���ł������B�{���́A���̌������j�ƌ��I�ȗ��j�̃n�U�}���s���Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
|
|

[ ���� ]
|
�u���b�N�z�[�N�E�_�E���q���r�\�A�����J�ŋ����ꕔ���̐퓬�L�^ (�n���J������NF)
�E�}�[�N �{�E�f��
�y���쏑�[�z
�������F 2002-03
�Q�l���i�F 693 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 693 �~�i�ō��j
�����i�F 100�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E�}�[�N �{�E�f��
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4.5 4.5
 �����������������i �����������������i
���̍�i��1993�N�Ƀ\�}���A�ŋN�����ČR�̎��s����������������i�ł��^�C�g���ɂ�����ʂ莩���͓ǂ�ʼn����������܂����B ���t�ł͌����\���܂��ǂ��Ɖ��Ƃ������Ȃ������ɂȂ�܂����B���͗ǂ������̂������ɉ�������̂��Ԉ���Ă����̂��c�ǂl�X�ɂ���ĕς��Ǝv���܂��B
 ���� ����
��15�l����������̂ŒN���N�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������m��܂���B�ł������������Ζʔ����Ǝv���܂��B
 BHD BHD
�����݂̂̃��r���[�������C�Ƃ����̂��ςȋC�����܂����Q�l�܂łɁD���̖{�͎j���Ɋ�Â��ċL�q����Ă��邱�Ƃ́C���̃��r���[�������̊F����͂����m���Ǝv���܂��D
�f�扻������Ă��܂����C�f��ł̓X�g�[���[�����o�����߂ɂ������̓_��(�j����)�ύX����Ă��镔���������Ȃ��Ă��܂��D ���ۂɂ��̂Ƃ��Ƀ\�}���A�ʼn����N�������̂��C������x�̌R������j������m���͕K�v�ɂȂ�܂����C���̖{��ǂ߂Η����ł���Ǝv���܂��D �A�����J�������l���C����ڕW�ɂ��Đ��E�e�n�ɐi�o���Ă���̂��D
������`�����ł͂Ȃ��C��ނ�̍l���鐳�`��̂��߂ɓ������Ƃ�����C�Ƃ����ǂ���ł͂Ȃ��ł��傤���D �����̍����猩�����͈قȂ������l�ς̉����t���ɂȂ邱�Ƃ�����܂����c �R�����A�Ƃ������͗��j���A�Ƃ����ϓ_�Ō���Ɩʔ����Ǝv���܂��D
|
|

[ ���� ]
|
���U�\�O���̓����Ɛl�Ԃ̏��� (���l��NF����)
�E�X�{ ���v
�y���l�Ёz
�������F 2005-06
�Q�l���i�F 870 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 870 �~�i�ō��j
�����i�F 84�~�`
( �ʏ�4�`5���ȓ��ɔ��� )

|
�E�X�{ ���v
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@�@ 0
|
|

[ ���� ]
|
�u���b�N�z�[�N�E�_�E���q��r�\�A�����J�ŋ����ꕔ���̐퓬�L�^ (�n���J������NF)
�E�}�[�N �{�E�f��
�y���쏑�[�z
�������F 2002-03
�Q�l���i�F 693 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 693 �~�i�ō��j
�����i�F 150�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E�}�[�N �{�E�f��
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 5 5
 ����Œm��f��̈̑傳 ����Œm��f��̈̑傳
���͉f�悩�猴��ɓ��������ł���B
����Ŋ��������Ƃ́A�f��ł̓g���E�T�C�Y���A�����������������̂�������������Ă����Ȃ��A�Ƃ��A�W���V���E�n�[�g�l�b�g�̖����G���b�N�E�o�[�i�̃f���^���m�̖����A���݂��Ȃ����O�������̂��Ȃ��A�Ƃ��B�����E�G���_�[�h�̉�������Q�ė��@�̑��c�m�}�C�P���́A���ۂ͂ǂ��������Ƃ���֘A��Ă�����āA�f��̖���ʂł���u�}�C�P���A�����ČN�����̂ĂȂ����I�v�ƃw�������Ӓ��Ăт��������Ԃ̐��́A�S�R�������Ă��Ȃ������A�Ƃ����̂�������Ƃ������肵���B�Ȃɂ��낱�̏�ʂ͎��̋����̃|�C���g�ł���A���ꂱ�����f��̃e�[�}�ł���������B
���k�p���c�A�Ƃ����̂��f��ɂ͏o�Ă��Ȃ������̂ŁA���ЂƂ����������Ă݂������̂��B�������A����������Ȃ����A���͌����ǂ�ł���ɁA�f��u�u���b�N�z�[�N�_�E���v�̋r�{�Ɗē̗͗ʂɓ��𐂂ꂽ�̂������B
���ꂾ���̐l�����f��ł����̂ɁA����Ƃ��͓������Ĉ�l�i�ɂ��Ă݂���A�����̕��m�̏ے��ƂȂ�悤�ȑ��݂��Ȃ��o��l�������o������A��ڕ���_������ďo�����ʂŎ��ʕ��m�̑_����ʂȂǁA�R�l�ڂŋC�t���ꂿ������A�Ƃ�������ʂ����o������A����ɂȂ������ɁA���̎�r���Ⴆ�n���Ă���B
���K�f�B�V���ł̍��Ƃ����̂́A���ׂĂ������ق��ɓ]�����čs�����B
����ɂ���āA�����Ɏ���܂ł̏����ȍ��̐����ɂ��A�i�ߕ����i���Ă����A�Ƃ������Ƃ��悭�킩��B
�u�u���b�N�z�[�N�_�E���v��ǂނȂ茩��Ȃ肵�āu������A�����J�̌R����`�́v�Ɣᔻ��������A�Ƃ��������ɂ́u�݂�Ȃ���������Ƃ肠�������������́H�v�ƕԂ������B
���������̓��ōl���������ƂƂ����̂́A�������B����͎��s�����R�����ł���A����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��A�Ƃ������ƁB
���̍�킪�A�������Ă����Ƃ�����ǂ����낤�B����ł��A�u������A�����J�̓_���Ȃv�Ƃ݂�Ȃ������̂��낤���B
 ���ꂪ�{�C�̐퓬 ���ꂪ�{�C�̐퓬
���̖{��1993�N�ɂ������ČR�̍��̎��s���������{�œǂނƂ��̍��ɎQ�������ČR���m�B�������Ă�������y�ɏI���Ǝv���Ă�����킪���Ԃ��o�ɂ�ň��ȕ����������Ă������Ȃǂ�������Ă��܂��B���Љf��ƈꏏ�ɔ����Ă݂ĉ������f��ł킩��Ȃ����͂��̖{��ǂ߂킩��܂�
 �f��Ƃ͈�����ϓ_���� �f��Ƃ͈�����ϓ_����
���̏����ɂ͎��ۂɐ���̌������Z�l�������ނ����Ă��邽�߁A
�č��̈���I�ȉ��߂ł͂Ȃ��A�ނ�ɂ͔ނ�Ȃ�̗��R������
�ĕ����U�����Ă������Ƃ������Ă������B
�f����������A������͕ČR�̈���I�ȓ��e�ƂȂ��Ă���
�����̕��G�ȏ�S�������Ă͂��Ȃ��B
�f���������������ǂ�ł��Ȃ��A�Ƃ����l�ɂ�����Ƃ��ǂ�ł��炢��������ł���B
 �R������̓����`������j�� �R������̓����`������j��
a?"a??a?�Pa-'a?2a?Ra�C�a1?a?'a??a?\a?��a??c���e��Ca?Ra??a?-a?\a?!a?3a??a?aa??a�?a??a??a??a??c?Ra?Ra??a?��a??a??a??e�ʁEa?"a?��a?|a??a??a??a??a?��a?aa?��a?��a?��a?|ao?a?Ra?2a?�Na??a?'a??a??a?|a??a??a??a�?a?"a?Rec�}a??aR?ec�}a?�Na??a??a?"a?�Na?'a??a??a?|a?�Pa?aa??a?aa??a�?a?"a??a??a?��a??a?|ao?a??a?Ra?�Pe�?a�C�Cc??a-1a?Re|-c?1a??a??e|?a??a??a?Ra?��a?aa??a??a?!a??a??a�?a??a??a?aa?��a?'a?Ra?-a??a??a??a??a?|a??a?aa??a?�Na?"a??a?��a�?a?aa??a?"a??a?'a?�Ca??a??a??a�?a?�Na??a??a??e�...a?Ra�?a??a??a??a??a?��a?|a??a??a�? a-|e��...a?-a??a?'a?'a?��a?2a??a??a�?a��!a�...a?�Na��2e-"a??aRoa??a??a?|a??a??c�}3e��?a?Ra??a?��a??a??a?ca??a?1a??a?��a??a?3a?�Ca?��a??a��-a�?a...��a����a?Ra??a�-a??a??a??a?"a?�Na?aa??a??a�?a??a??a?aa?��a?Raooa�...a?��a?�Na?��a?|a??a?"a?Ra?oa?\ao?a??a?ca?"a?aa??a'3a?'a??a??a?Ra??e�?a??a??a??a??a??a??a�?a??a??a?aa?��a?'a?Ra-��e�...a?��a?Ra?��a??a??a?��a�'c??a?��a??a??a?"a?�Na?'a??a??a?|a?�Pa?aa??a?aa??a�? a-?a?-a?Re??a??a??a?�Ca?Re��?ao?a��?a...\a?Re?��a?-a??a?'e�?a??a??a??a??a??a??a�?a?��e|?a�N!ccoc??a?'a?-a?'a??a?3a??a??a??a?��a??a?��a!?3a�?a??a?-a?|a??a?ca?�Pa?�Na?�Pa??a??e??a??a??a?Ra?��a??a??a�?a?"a?Ra?��a??a?aa??a?��a??a??a?"a?Ra?|ao?a?�Paooa�...a?Re�N?a?��a??a??e-?a??a?|a??a??a?"a?�Na?��a?aa?��a??a??a??a?-a??a?aa??a�?a-'a?2a?�Ca?��a??e!?a?-a??a??a??a"?a??a�?
 �f���z�����Ȃ���ǂނƂ�胊�A���Ɋ����܂��B �f���z�����Ȃ���ǂނƂ�胊�A���Ɋ����܂��B
��ނɂ���ďW�߂��������Ĉ�{�̏����Ƃ��Ďd�グ��B�悭�������܂łƊ��S���܂����B�����Ȑl�����o�ꂷ��ɂ��ւ�炸�A���ꂼ��̐S��܂ł��k���ɕ`���Ă���A�f���ɂȂ��Ă��Ȃ������Ƒ�����l�A�\�}���A�s���A�m�o�n�W�ҁA�ʂĂ͕Ė{���܂Ńu���b�N�z�[�N�ė��̎����ɂ܂�鐔�X�̃G�s�\�[�h��������Ă��܂��B�@�����ĒN�����m�肽���Ǝv���������̓^�����u�����v�Œm�邱�Ƃ��o���܂��B�@
|
|

[ ���� ]
|
�\�A�����F�ɐN�U������ (���t����)
�E���� �ꗘ
�y���Y�t�H�z
�������F 2002-08
�Q�l���i�F 570 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 570 �~�i�ō��j
�����i�F 140�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E���� �ꗘ
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4.5 4.5
 �E���̐l�͂��̖{��ǂނ̂͐h���ł��낤 �E���̐l�͂��̖{��ǂނ̂͐h���ł��낤
���j�ɗ�����Ȃ��A���E��̈��ň����ȑ���{�鍑�R�B
����ł��E���ɂƂ��ẮA����{�鍑�R�͋����Ă������傦�����`�̌R���ł�����������ȁH
�E���͂����咣���邾�낤�c�B
�u���Ƃ����̂́A�G������̎��_�ł����āA
�@���{�l������{�鍑�R�����Ă�肷��͕̂ςł͂�?��܂��H�v
�ςł͂���܂���B
���a�̑���{�鍑�R�́A�V�c�����R���ł���A
���{���������ׂ̌R���ł͂Ȃ������̂ł���B
�A�����J�������𗎂Ƃ����ׁA���̗����l���ɂ��������\�A�����B�ɐN�U���܂������A
����{�鍑�R�͖��B�J��c�������ĂĂ������ƓP�ނ������ȁB
���E�j�Ń��W���[�Ȉ��̃i�`�X�h�C�c�ł����A
�s�F�Z���ɂȂ�����́A�f�[�j�b�c�̓h�C�c�����������ɋA�҂����邱�Ƃ�D�悵�āA
�����Q�O�O���l�ȏ�̖��Ԑl���~�����̂ł��B
���a�̑���{�鍑�R�͂P�O�O���l�̖��B�ږ��c�������Ăē����A��Ƃ́A�p�ł��ȁB
�헪��̖����A�t�H�̑���{�鍑�R�̎w�����̖��\�U��͗L���ł��邪�A
�{���͉��̖��\�ɂȂ��������l�@���Ă���B
���\�Ȏw�����Ƃ����̂́A���f�͂���������ł���B
���́A���f�͂������̂��Ƃ����ƁA
���m�̏�ɐӔC������������ł���B
���ۖ@�����炵�ē��I�푈�����������̑���{�鍑�R�́A���E�������^���ꂽ���A
�S�Ƃ��C�G���[�����L�[�ƌď̂���鏺�a�̑���{�鍑�R�́A���ׂ����ۖ@�ɖ��m�ł������Ƃ����̂��^���炵���B
���E�̏펯��m�炸�ɁA���{�͐_�̍��Ƒ��������̂��A�S�Ă̎��s�̖{�����ˁB
���{�����ň������Ƃ��Ă��A
���\�s�N����j���ĐN�U���Ă����\�A�������Ƃ������͂������܂��B
���E��̈��͓��{�R�����A���E��̈��̓\�A�R�ł��O�j�ł��B
�������A�\�A�R�͈����ł͂���܂���B
���{���~�������W���P�T���ȍ~���A�\�A�R�͖��B�ŋs�E�𑱂��܂������A
�s�E���Ă��n�j�A�V�x���A������n�j�Ƃ����������������ɔP����o���̂Ŋ������܂����i�m
 �Ȃ��A���ɂ��Ă��Ȃ������̂��H �Ȃ��A���ɂ��Ă��Ȃ������̂��H
�@����Ɍ����̓������ꂽ���ɁA����I�ɕs�����j���Ė��B��k���S���ɐN�U�����\�A�R�̐U�镑���́A�ƍߎҏW�c�ɓ������B
�@�X�ɁA���̌�A���{�l�̑����ɓz��ɓ����������^�����B
�@�S�������đ����m�푈�̐ӔC�����{�ɂ������Ƃ��Ă��i���͔F�߂Ȃ����j�A�\�A�R�����B�ōs�Ȃ������Ƃ́A�푈�ȑO�̔ƍ߂ł���B
�@���̃\�A�����ۘA���̏�C�������ł���A���̌�A���܂��܂ȓ��������̈���̓����҂ł��������Ƃ��A��X�͖Y��Ă��Ȃ����H
�@���{�ɂ����钆���́u�싞��s�E�v���c�_����Ȃ�A�����ڐ��Ń\�A�R�̂����s����_��Ȃ���o�����X�����܂��B
�@�c�O�Ȃ���A���̌��_�E�́A�}���N�X���[�j����`�̐i���I�����l�Ɏx�z����A�o�C�A�X���������Ă����̂ŁA���̔ߎS�Ȗ��B�̏o�������������Ƃ��A�ᔻ���邱�Ƃ��Ȃ������B
�@��Q�ɂ���ꂽ���X�̖��O���v���ƁA���̐i���I�����l�̍߂͑傫���Ǝv���B
 �\�A�R�́A���B�œ��{�̏�����q���ɉ����������H �\�A�R�́A���B�œ��{�̏�����q���ɉ����������H
���N�A�W���X���ɐ���ƁA�e���r�̃j���[�X�́A����̌�������`����B�����A���̓��i�W���X���j���A�P�X�S�T�N�i���a�Q�O�N�j�ɁA����Ɍ������������ꂽ���ł��鎖�́A�`����̂ł��邪�A���̓����i�P�X�S�T�N�j�W���X�����A�\�A�̖��B�N�U�̓��ł���������`����}�X�R�~�́A�ɂ߂ď��Ȃ��B����́A��́A���̂Ȃ̂��낤���H�|�|�P�X�S�T�N�W���X���A�\�A�́A�����܂��L�����������\��������j���āA���B�ɐN�U�����B�����āA�N�U������X�ŁA�q����V�l���܂ށA�����̓��{�̖��Ԑl���A�����ʂɎE�C�����̂ł������B���A�q�����܂ށA�����̓��{�l�������A����ė����\�A�R�̕��m�����́A���鏊�ŁA�����A�֊������̂ł������B���̍ۂ̔ߎS�ȏ́A�����Ƃ͌`����������̂́A���̐��̐����n���ƌĂ��ׂ����ł������B�|�|�\�A�������A���{�̃}�X�R�~�̑����́A���̂��A���̃\�A�R�̖��B�N�U�ɂ��ߌ�����肽����Ȃ��B�Ⴂ�l�����́A�{�����܂߂��P�s�{��R�����āA�����A���{�̎q���⏗�����A�\�A�R�ɂ���āA�ǂ�قǂނ����ڂɑ��킳�ꂽ�����A�m���ė~�����B�i�������I�E���Ȉ�^�\�A�R�����B�ɐN�U����������U�O�N�ڂ̓��Ɂj
 ���{�̖���Ԃ�ƃ\�A�̔� ���{�̖���Ԃ�ƃ\�A�̔�
�{������́A���{�̖���Ԃ�ƃ\�A�̔��A�������ǂݎ���B�܂����{�����A�Γ��Q������łɌ��߂Ă����\�A�ɑ��ďI��̒�����H�삵����A�|�c�_���錾����������~�����Ǝv������ł������ƂȂǂɌ�����A���ۏ�̌����A���ۊ��o�̌��@�A�y�ώ�`�A���ӔC��`�ȂǁA���ƖŖS�̊�@�ɍۂ��Ă̑̂��炭�͕���Ԃ����ł���B���̂Ƃ��Ɠ����悤�ȏ́A���݂��i�s���Ă���̂�������Ȃ��B �\�A���s�������B�ɂ�������{���Y�̏�����V�x���A�}���́A�č����܂߂��A�������ł����������܂ŗ\�����Ă��Ȃ��������Ƃ���A���{�̖��\����̂�������Ƃ͌�����Ȃ��B���̎��̂��Ƃ���\�A�i�����V�A�j�̖{�����ǂݎ�����ł���B�\�A�̎Q��ɂ���Ĕ������Q�͌v��m��Ȃ����A���߂Ă�������P�Ƃ��āA����̑��V�A����ɐ������ė~�����Ɗ肤����ł���B
 ���\�͍߂ł��� ���\�͍߂ł���
�@���������āA�ɂ܂��߂��ēǂݐi�߂�̂��h���ł��B�Ȃ��A�ǂ������o�܂Œ�������j���ă\�A���˔@���B�ɐN�U���ė����̂��B���̎����B�ʼn����������̂��B�����̐^�������\�����̎����ɂ�薾�炩�ɂ����B �@�����̓��{�l��]�̋������́A�푈���n�߂����Ƃ����A���̏I��点���̕��ɂ�葽���̖�肪����Ǝv�����B���{�́A�\�A���Վ�ἁX�ƑΓ��Q��̏��������Ă���̂��m�炸�A�\�A�ɛZ�тւ炢�A�a��������˗�����B�������U�X�ł炳�ꂽ���������̓����͐��z���������B�\�A�Q��K���Ƃ����������̏����Ȃ���A��]�I�ϑ��ɂ���Ă����َE���A�܂����������A���ʂƂ��Ċ�P���������B �@������搂�ꂽ�֓��R�́A�������̏X�Ԃ��N���A���J�ɂ܂݂ꂽ�Ŋ����}����B����A�֓��R��ӂ߂�͍̂���������Ȃ��B�V�c�̌R���ł�����{�R�ɂ͖��Ԑl�ی�͍ŏ�����O���ɂȂ������B�����h��ɕs���ȐV�����̂āA�ʉ��ł̌}������}���Ă̓P�ނ������̂����A���Ԑl���猩���玩�����������̂Ăē������Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA�֓��R�̎�͖͂w�Ljꔭ�̒e������ƂȂ��~�������B�����̑����̓V�x���A�}���̐h�_���r�߂�B�����ĊJ�����͏W�c�����A�����x�ꂽ���Ԑl�̓\�A�R��ّ��Ɖ������n�����ɂ��A���D�A�\�s�A�E�l�A�����Ȃǂ̎d�ł�����B �@���҂́A�u�푈�ɐ��`�ȂǂȂ��v�ƒ��Ȍ��t���J��Ԃ��A���̓r�����Ȃ��ߌ��̗B��̋��P���ƌ������A����Ȃ��Ƃ����A���{�鍑�̐̂��猻��Ɏ���܂Ŏ����Ă��Ȃ��A���{�l�̖��ӔC�̎��A�y�ώ�`�A���������Ƃ������ׂ𑁋}�ɂȂ�Ƃ����邱�Ƃ��������P���낤�B
|
|

[ ���� ]
|
�u�����H�[�E�c�[�E�[���\SAS���m�����p�ݐ푈�̑s��ȋL�^ (�n���J������NF)
�E�A���f�B �}�N�i�u
�y���쏑�[�z
�������F 2000-10
�Q�l���i�F 924 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 924 �~�i�ō��j
�����i�F 480�~�`
( �ʏ�4�`5���ȓ��ɔ��� )

|
�E�A���f�B �}�N�i�u
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4.5 4.5
 ���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ� ���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ�
SAS�̔C���Ń}�N�i�u���܂߂�8�l�̓C���N�ɐ������邪�A�s�^�Ȑl�I�~�X�̘A���Ŏ��s��]�V�Ȃ������B����͔����ɂ��Ă��A���̓��[�_�[�Ƃ��ď�Ɍ��f�𔗂�����d�Ȃ�B����Ȏ��A���m�͐Êς�������Ȃ��B��邩���邩�A�܂萶��������I�����˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�����X�͉����ɂ����Ă��ɗ����ꂪ���ŁA�����Ō��f��������B�l�͂��̒����ŁA�҂��Ă��邾���ł͈�����ŊJ�ł��Ȃ����Ƃ�Ɋ������B����ɂǂ�ȂɌ��ꂵ���Ă��A������������Ɋr�ׂ�Ή�X�̂���ȂǛ��݂����Ȃ��̂��B�������X�����Č��f�ł���͂����B
 �^���͊�Ȃ� �^���͊�Ȃ�
��������H�j��ō����x���̐�L���Ǝv���B
�����Ƃ������L�^�͐��ɏo�ĂȂ��B�푈�ɂ�����C���̐��s�͔閧���ɍs������̂�����B�܂��͐������ڗ����Ȃ����Ƃقǐ���������B
�Ƃ����Ӗ��ł͖{���͎��s�̋L�^���B
��L�Ƃ����Ƃ��Ȃ蒷���X�p���ő�K�͂Ȑ푈�Ǝ��ꂻ�������A�p�ݐ푈�ɂ�����SAS��8�l�ɂ����̋L�^�B
�����Ă��̋L�^�͌l�̎�ςŕ`����Ă���B�Ƃ͂����Ă����҂͋q�ϓI�ɂȂ�悤���Ӑ[���C�����Ă���̂����B
�㔼�͎�ςȂ͂������A�q�ϓI�ɏ������Ƃ��Ă��镶�̂����|�������B���̂��ƌ����Ɓc�B
�܂莩�������v����鍉��A�\�s�̘A���̋L�^�Ȃ̂Łc�B������������̌P�����Ă���̂�SAS�����Ȃ킯�ŁB
�Ƃ��낪�����ȒP�ɂ����Ȃ��̂��l�ԂŁA�푈�ŁA����ɋɌ���ԂȂ̂ŁB���肪���肾���B
���O�̍�헧�Ă̑ō����A�����ƃA�N�V�����O�ɍs���`�F�b�N�̂����A��O���킵���d�ʁE�����i�⋋�����Ȃ��̂ň�l100�L���߂��I�j�B
�A������^���N�܂Ŏ��������̂ł��B�A�ō�킪���̂�h�����߁B�A�͓������̑��ɉe�����c���A�G�Ɍ����郊�X�N���オ��炵���i�n�`�ɂ��̂����j�B
���A���߂��郊�A�������˂����������x���Ȃ̂ŁA�C���������̂�ʂ�z���Ă������Ɏ���邵���Ȃ��B�܂��͂���Ӗ��A�n���n�������C������B
�ł����ꂪ�푈�c�B
�����A��s�@�Ō쑗���ɕĉp�̗��@���������T�[�r�X�ɂ͊����B
 �q�g�́u�ӎu�v�Ɓu���ԁv������A�����܂ŋ����Ȃ�� �q�g�́u�ӎu�v�Ɓu���ԁv������A�����܂ŋ����Ȃ��
�v����ɁA���s�����~�b�V�����̈ꕔ�n�I���������{�ł���B�������u�M�d�ȋ��P�́A�ނ��뎸�s���瓾����v�킯�ŁA���`�����`���ʔ����B
�{�����G�ɁA�������x�^�Ŗڂ��B���ꂽ���҂⓯���̎ʐ^���ڂ��Ă���B�����Ђ���_�T���������ނ��ꂵ���BSAS�͓G�n�����̈�T�ԑO���畗�C�ɓ���Ȃ��B���R�͖{���`���ɏo�Ă���̂œǂ�ł��������B�ނ��ꂵ���g�Ȃ�ɂ��S�ė��R������B�o���ƁA�l�������ꂽ�v�����̌��ʁA�ނ�͉f��ɓo�ꂷ��J�b�R�C�C���ꕔ���Ƃ͂������ꂽ�_�T���i�D�Ő키�̂��B
�{���ł́A�ނ�SAS�̍s���̗��R��ړI���A���̒m�����Ȃ��f�l�ɂ������ł���悤�A���ؒ��J�Ȑ��������Ă���B���������̐��������l�߂Ŗʔ����B��̉��ǂ̗����ƁA�ނ炪���ۂɑ��������劦�g�łǂ�ȓ��̏Ǐo�����̕`�ʂȂǁA���ɏG��B����ނ̐������ʔ����A�⋋�̂Ȃ��Q������ł̎g�����ȂǗޏ��ɂ͂Ȃ��B���̃X�^���X�͏I�n�ς�炸�A�ߗ��ƂȂ��č������ۂ��A�����Ǝ��ۂ��W�X�Əq�ׂ���B���낵���\�́B����ɖ����ŗ������������҂̈ӎu�B�����B
���҂͊w���F����16�ŗ��R�ɓ��������s�Ǐ��N�B�������{���̖ʔ����͑��Ƃɂ��S�R�����Ȃ��B�܂����m�I���BSAS�̌������P���ƌo�����f���炵�����@�͂ƕ`�ʗ͂҂ɗ^�����̂��B
�����f���炵���̂́A�ނ�́u�ӎu�v�͂͐��܂���ł͂Ȃ��P���̐��ʂł��邱�Ƃ��B�l�Ԃ͂����܂ŋ����Ȃ��\��������A�Ƃ������Ɓi�������Ă����Ɓj�B�����āA�ǂ�ȂɌ������ł��u���ԁv�Ƌꂵ�������������Ƃ��ł���A�����Ƌ����Ȃ��B�Y�����ł̒��Ԃ����Ƃ̕`�ʂ͖{���ɋ�������B
���ɋ��낵�����e�̖{�ŁA�ǂނ̂��h���Ȃ镔�������邯�ǁA���͋����E�C�Â���ꂽ�B�{���͉��S�N�o���Ă��Â��Ȃ�Ȃ��͂����B�l�ޕ��Ղ̉��l��`�����A�P���������������炾�B
 �^���͊����ł��B �^���͊����ł��B
�s��ȓ��e�ł��B���b�ɂ͂Ȃ��ْ���������܂��B
�n���̌P�����猻���̐푈�A�q�[���[�̂��Ȃ��A����̋�ɁE�E�E
�b�̓��e�����A���ɓ`���܂��A��C�ɓǂ݂܂����悩�����ł��B
 �����m�邽�߂� �����m�邽�߂�
�{���͂܂����ƂĂ��ǂ݂₷���A�����炭�p�����R�l�̎����A�����̂悤�ȊȌ����ĂȂ��̂Ȃ̂ł��傤�A�h�L�������g�̕��̂Ƃ��ĂЂƂ̗��z�I�ȕ��̂悤�Ɏv���܂��A�p�ݐ푈�́u����v���ǂ̂悤�ł��������A�Ɋւ���M�d�ȋL�^�ł��A�J���[�O���r�A���ǁA�`���̑����ЌR�̏W�܂�̈�ق̕`�ʁA���ꕔ�����̓{�[���y�����������ɒZ�����M�����{���g�т���Ƃ��A�A�̎n���̂��߂ɗe���p�ӂ���ȂǂȂǍׂ����`�ʂɃy�[�W���߂��邽�тɔ[�����Ă��܂�����ł��A �����ɌJ��Ԃ��u�ɂ����E����v�Ɋւ���L�q������邱�Ƃ��ƂĂ������[���Ǝv���܂����A�ǂ����œ����ɂ����Ǝ�����������ǂL��������ȂƁA�v���o���Č�����g���E�n���X�u�n���j�o���v�ł����A���œ����ʂ����߂ɂ͎��́E���͂���Ώ����̂悤�Ɏv���Ă��܂������A�ɂ߂ĎE���Ƃ������ŌȂ̐��Ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ�����k�o�܂ł����Ⴆ�n��A�������͚k�o���Ⴆ�Ȃ���ΐ����c��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����̂��Ɣ[���������܂����A�@�n���j�o���̓��l�̋L�q�͖����Ɏ�l���̓����Ɋւ���t�F�e�B�V�Y�����Ǝv���܂����A �{���Ɠ����^�C�g���ŁA���������ŗB��l�A�ߗ��ɂȂ炸�ɐ��҂����������������{���o�ł���Ă���A������̓C�M���X�ʼnf�扻������܂����A���{�ł������^���E�r�f�I�ɂȂ��Ă��܂��A
|
|

[ �P�s�{�i�\�t�g�J�o�[�j ]
|
�푈���Ł\�A�����J���R����`��E���o���Ȃ��{���̗��R
�E�W���G�� �A���h���A�X
�y�����o�Łz
�������F 2002-10-10
�Q�l���i�F 1,365 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 1,365 �~�i�ō��j
�����i�F 243�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E�W���G�� �A���h���A�X
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 4.5 4.5
 �R�����ƃA�����J�̖{���̎p�ɔ���D�� �R�����ƃA�����J�̖{���̎p�ɔ���D��
�A�����J���ό��ł͂Ȃ��A�u�ώ@�v����@������Ƃ�����l�ł���A
���̍��͂̃C���[�W�ɔ����āA����E��Â����Ȃ��l�X�̑����A
���|�I�ȕn�x�̊i���A���]�ƌĂ�ł������x���̂Ȃ��l�ȁA�R����`����������Ă���
�u�A�����J�ꍑ��`�v���^��Ȃ����ʂ̐l�X�B
�x�z�ҊK�����l�n�����ɁA�Ƃ��Ɍ����邠�̖ҋחނ̂悤�ȖځB
�E�E�E�����Ŋ����邱�Ƃ��ł������낤�B
�Ɨ�������������A����������Ύ��������̉^�������߂錠��������������A�����J�l�́A
���̂��ׂĂ̐l�X�̉^�����A�����J�l�����߂��Ǝv�����B������u�^�������imanifest destiny)�v�ł���B���ꂪ�A�����J�Ƃ������̂��ׂẴX�^�[�g�������B
�ꕪ�ɂP�O�O���h���A��ƂɔN�ԂS�O�O�O�h���̌R����p����������A�����J�B
�푈�̗��ŕs�K�̂ǂ��ɗ��Ƃ����̂́A�ǂ̎���ł��ǂ̍��ł��A��҂Ȃ̂��B
���ĒN�����u�A�����J�̐��`�ɂ͕K���\�͂������v�Ƃ��������A
�{���̃^�C�g���u�푈���Łv�ƌĂ����K�ł��낤�B
�A�����J�͕ς�邩�H�ς����邩�H
���E�̕��a�Ɛl�X�̍K�����l����Ƃ��A���̍��̂��Ƃ͔����Ēʂ�Ȃ��B
���̖{�ł́A���������N�ɓn���ď������w��ł������̂��܂Ƃ߂ďЉ��Ă���B
�����܂����u���̖͂����v���T�ς��邱�Ƃ��ł���B
���̖{�̗��\���Ƀu���C�Y�E�{���y�C���Ƃ����h�I�t�B�X�E�I�u�E�A�����J�h��
�f�B���N�^�[�������Ă���悤�ɁA�u�i�A�����J�́j�R����`���q�ɂ��ĂP�Q�N�Ԃ�
������������Ŋw�Ԉȏ�̂��Ƃ��w�Ԃ��낤�v�ɔ[������B
���̌��t��a�ꂽ���̖{�̓ǎ҂ɑ����Ă��ԈႢ�͂Ȃ��Ǝv�����e�ł���B
 �x�l���̂��߂ɂ́A��i��I�Ȃ��� �x�l���̂��߂ɂ́A��i��I�Ȃ���
�x�l���̂��߂ɂ́A�푈�����}��Ȃ��Ƃ����n�C���X�N�E�n�C���^�[���̌��_��
�����ɂ���܂����B�{����ǂނƁA�A�����J�͉��̐푈�𐋍s����̂��A�푈��
�ǂ�Ȃ��Ƃ����āA�ǂ̂悤�ɕx���g�債�Ă������A�s�u�V���Ȃǂ̃}�X�R�~�ł�
�w�Ǖ���邱�Ƃ̖����A�B�ꂽ��[���M���m�邱�Ƃ��ł��܂��B�A�����J��
�Ƃ��Đ푈�Ƃ́A�x�l���̎�i�ł����Ĥ���̎�i�Ƀ^�u�[�͂���܂���B�C��
�f�B�A�������̋s�E�Ɏn�܂錚���Ɨ̓y�g��A���݂̐Ζ������l���Ɏ����
�ň�т��Ă��邱�Ƃ������т�����܂��B�]�k�ł����A�Q�吭�}�����m������
�������`���Ƃƌ����Ă��܂����A�푈�ɂ�鍑�x�g��̃C�f�I���M�[��
���a�}������}���Ⴂ�Ȃ��A���ʂ��Ă��܂��B
 �C���f�B�A������X�P�P�܂ł̌R�g��`�𒆊w���ł��킩��悤�ɐ����B���{�l���A�����J�ł̍Ĕ̂ɑ傫���e���B �C���f�B�A������X�P�P�܂ł̌R�g��`�𒆊w���ł��킩��悤�ɐ����B���{�l���A�����J�ł̍Ĕ̂ɑ傫���e���B
���̖{�́A�C���f�B�A�������̋s�E����n�܂��āA�X�P�P�܂ŁA�A�����J�������ɐ푈�ɂ���ċ����ɍ��͂��L���Ă��������A�����Ă��ꂪ���E�ɗ^���������ƁA�����ɂ܂�����c�P���A���ɂ킩��₷������ł�����Ă���B
�������܂�b��ɂ��Ȃ�Ȃ��J�[�^�[�A���[�K�������̎���̃C�����E�C���N�푈�������܂��܂Ƃ܂��Ă��āA���܂���Ȃ���u��?�����������̂��v�Ɣ[���B���[�K�����AGE�̃R�}�[�V�����Ōق�ꂽ���҂������Ƃ��A�����哝�̂̃`�F�C�j�[���A�Ζ��@���Ђ̎В��������Ƃ��Ƃ�ł��Ȃ����������낢��łĂ���B
�����āA���̖{���łĂ����o�܂��������낢�B���������łɂȂ������̂@���Ĕ́B���̍ĔłɁA��������ݎ��ƗL�u�B���^��������������̂��B����ɂ���ăA�����J�����ł��̖{���ǂ߂�悤�ɂȂ�A���܂ł͊w�Z�Ȃǂł��Q�l���Ƃ��ĂƂ肠�����Ă���Ƃ����B
���{�l���A�����J�l�̖ڂ��o�܂����邱�Ƃɉe����^���Ă���̂��B
 ���炽�߂Ĉꋓ�ɂ������Ƃ�͂�V���b�N ���炽�߂Ĉꋓ�ɂ������Ƃ�͂�V���b�N
���̖{���Q�O�O�R�N�x�ł̂܂������ɂ�����Ƃ���A�����������{���Ă���
�Ƃ̂��Ƃ�m��ق��Ƃ������܂����B
�܂��A�����ɏ�����Ă��邱�Ƃ́A�����ꕔ�������ẮA�f���l���x��
�̉�b�ł͌��������Ă������̂ł����B
�������A�ꋓ�ɂ�������ɂ����Ɩ{���ɃV���b�N�B
�ł��A��ԏ����͈̂�ʂ̃A�����J�l�B���Ǝv���܂��B
���̖{�͂����ƁA����ƂƂ��ɁA�����������̒��u�Ȃ�Ƃ��������v�Ƃ�����M��������
�����ꂽ���́B
�ǂl�����������邩�������Ȃ�ɖ�����āA�����Ȃ�̈ӌ��������������ɂȂ�
�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�l�Ƃ��ĉ��������Ȃ����v�A������ƍl���āA�����Ȃ�Ɋ���
��ƂƂ��ɁA���낢��Ȃ��̂��݂���A�ǂ�A�o�����Ȃ���A�q�ϓI�ȑԓx��
�g�ɂ������Ǝv���܂����B
�����N���邩�킩��Ȃ��Ƃ������z�����Ɠ����ɁA���߂āA�푈�͌����Ǝv���܂����B
 ���̖{�̌��삪�A�����J�ŕ��y���邱�Ƃ�]�݂܂��B ���̖{�̌��삪�A�����J�ŕ��y���邱�Ƃ�]�݂܂��B
�@�}���K�ł��̂ŊȒP�ɓǂ߂܂����A�O�O�ɒ��ׂ�ꂽ�j���Ɍ�����������Ă���̂ŁA
�A�����J�̒鍑��`�E�푈�i�N���j�̗��j�̊T�v�������ł��܂��B
�@�l���A���Ɋ������̂́A�}�j���t�F�X�g�f�X�e�j�[�imanifest destiny)
�u�L���X�g���k�ɂ��V�嗤�̊l���ƊJ���_�ɗ^����ꂽ�����Ȏg���v�Ƃ���l�����A
���̍l�������g����߂��Ă����Ɖ�������Ă�����������邱�ƂɂȂ��Ă��܂�Ȃ����ƁD�D�D�D
���낵���ł��B
�ŋߓǂu�A�����J�̋��E���{�v�փ����E�~�A�[�Y�����ꏏ�ɓǂ�Ō�����Ɨ��j�ɑ��铴�@�͂�
�{���̂ɗǂ��̂ł͂Ǝv���܂��B
�@���̖{�A�������A�����J�Ŕ��튈���ƒ��S�ɂQ�������ꂽ�Ƃ̎��ł����A�����ƕ��y����
���̍��^������傫�Ȃ��˂�ɂȂ�Ɨǂ��ł��ˁI
�@
|
|

[ ���� ]
|
���l���L (�����܊w�|����)
�E���� �^��
�y�}�����[�z
�������F 2004-11-11
�Q�l���i�F 1,365 �~�i�ō��݁j
�̔����i�F 1,365 �~�i�ō��j
�����i�F 998�~�`
( �ʏ�24���Ԉȓ��ɔ��� )

|
�E���� �^��
|
�J�X�^�}�[���ϕ]���F�@ 5 5
 ���肬��̏�Ԃł̎����̑ԓx��z�����邱�� ���肬��̏�Ԃł̎����̑ԓx��z�����邱��
���̓��L�̎j�������Ƃ��Ă̈Ӌ`�ɂ��ẮA�R�{�������u���{�͂Ȃ��s���̂� - �s��21�P���v�ɏڂ����ł����A�����̌R���̏��𑽂�������ł���Ȃ���A���Ԑl(�R��)�Ƃ��Ĕ�r�I���Q�W�̂Ȃ��|�W�V�����ŗ�ÂȊώ@���ł��Ă���A�Ƃ������_�͊m���Ɉ�ǂ���ΉM���m�邱�Ƃ��ł��܂��B�{���̈Ӌ`�Ɍ��炸�A���̔w�i�A���͂Ȃǂɂ��ẮA�u���{�͂Ȃ��s���̂��v�ɗ]��ɓI�m�ŏڂ����l�@����Ă��܂��B����A�l�I�Ɋ��������Ƃ́A�Ɍ���Ԃł̐l�Ԃ̎��Ԃ͂������S�߂łނ������̂��A�Ƃ������Ƃł����B�{���ł��R���卲�Ƃ������h�ȏ��Z�̘b(��l����̐M�p�����A�M�O�̋����l�ł���A�n���Ȋt���̖��߂ɂ͌����ĕ������h������Ȃ������Ƃ���)���Љ��Ă��܂����A���������l�͖{���ɋH�������̂ł��傤�B�m���ɐ�����q���A�u�Ō�̐H���𑼐l�ɍ����o���邩�v�Ƃ��������肬��̖₢�ɁA���m�ɓ������鎩�M�͏��Ȃ��Ƃ����̖l�ɂ͂���܂���B�{���̌����͒W�X�Ƃ��Ă��邾���A�l�Ԃ́u�コ�v�Ƃ������̂����Â��l���������܂��B �R�{���������Ă��܂����A���������Ɍ���Ԃݏo���Ȃ��A�Ƃ������w�͂��܂����߂��邱�Ƃł���A�Ɍ��ɋ߂Â��ɂ�c���ꂽ�I�����͋����A���낵���h�����̂ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ��A�{����ǂނ��Ƃɂ���ĒɊ� = �Ǒ̌����܂��B�܂��A���肬��̏�Ԃł̎����̑ԓx�Ƃ������̂�z�����A���ْ̋����i�̐����̒��ňӎ����邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��ʏ�̎����̐����ԓx��l�ԊW�����ߒ����ЂƂ̎��_�ɂȂ�܂��B
 �푈����e���̎��ԁA�Ɍ����ł̓��{�l��I�m�ɋL�� �푈����e���̎��ԁA�Ɍ����ł̓��{�l��I�m�ɋL��
�W���[�i���X�g���W���[�i���X�e�B�b�N�ɑ��肷���A������c�߂����s������͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B����ǂ��납�A�P�Ȃ�`���������ɂ������̖ڂŌ������̂悤�ȋL���Ɏd�グ����A�S���̋��\�ƌ����������B�����Ƃ͔��ɁA�{���̓W���[�i���X�e�B�b�N�ɂȂ炸�A�������Ƃ����������Ƃ�����̂܂܂ɏ����A�˂Ă���B�{���ň�ԕ]�������ׂ��_�͂����ɂ���Ǝv���B �����ɏ�����Ă��邱�Ƃ͈�R�����̌��������Ƃɉ߂��Ȃ����A����ςɂƂ��ꂽ�W���[�i���X�g���������L�����A�푈����e���̎��ԁA�Ɍ����ł̓��{�l�ƌ��������̂�I�m�ɑ����Ă���Ǝv���B
 ��Ղ̊ώ@�L�^�B�ߎS�̉Q���ʼnȊw�҂̖ڂ͉��������̂� ��Ղ̊ώ@�L�^�B�ߎS�̉Q���ʼnȊw�҂̖ڂ͉��������̂�
�I��ԍہA���҂̓u�^�m�[��������C���Ƃ��镶���Ƃ��ăt�B���s���֕����B
�����œ��{�R�̔s�ށA�W�����O���ł̜f�r�A�����ďI��B���~�Ƃ��̌�̕ߗ�
���e���ł̐�����̌�����B���Ԃ̂������ɐg��u�����A�Ȋw�҂Ƃ��Ă�
��ÂȊώ@���Ȃ���A�]�v�ȏC����p�����H�L�ȋL�^���c����邱�ƂɂȂ����B
�{���𐢊Ԃɒm�炵�߂��R�{�������͂��̉��l�������Љ�Ă���B
�u�푈�ƌR���ɖ��ڂ��Ă��̉Q���ɂ���Ȃ���A��ÂȔᔻ�I�ȖڂŁA������
�������W���[�i���X�e�B�b�N�ɂȂ炸�A���ׂĂ�W�X�ƊȌ��A�I�m�ɋL���Ă�
��B���ꂪ�A�{���̂��ō��̉��l�ł���A�����炭�B�ꖳ��̋L�^�ł��낤
�Ǝv���鏊�Ȃł���B�v
�܂��R�{���͉���̂Ȃ��ŁA���~��̕ߗ����e���ŁA�W�����O����������
�����Ȓj�B���A���Ƃ����Ղ��ꈬ��̖\�͒c�I�O���[�v�̔z���ɑg�ݍ��܂�A
�R���g���[������Ă����l���L���������ɂӂ�A���݂̖��Ƃ��Ă��Ȃ�����
�Ă���Ƃ����B�m���ɂ��̒ʂ肾�낤�B�����K�ǂ̏��B
 �Җ]�̕����A�[������ �Җ]�̕����A�[������
�R�{�����u���{�͂Ȃ��s���̂��v��ǂ�ňȗ��A���̃x�[�X��
�Ȃ����{�������Гǂ�ł݂����������A���̂��ѕ�����������
���҂������ēǂ�ł݂��B
�@
�{���͒��҂��t�B���s������ő̌��������{�R�̍s����������
����Ă���B�܂����{�R�ɏ]���Đ�������N�l�A��p�l�A
�t�B���s���l�̂��Ƃ�����Ă���B������҂̕ČR��
���Ă����B�X�̘b�͂ǂ���S��łB�H�Ƃ��s����
���{�����F�R���m�E�������Ă��̓���H���b�A�E�W�̗O����
��e�̎��̂ɂ��܂ł���肷�����Ă���c���̘b�A
�h�{�����̂��߉���ɓ������Ƃ���S����ჂŎ����m��
�������݁X�Ɖ���̂Ȃ��ɒ���ł����b�Ȃǃt�B���s��
����͂����܂ŔߎS�������̂��Ɖ��߂Ďv���m�炳�ꂽ�B ����ɕߗ����e���ł̐��X�̑̌��ƌ��������҂̐l�Ԋώ@��
����ɐ[������B���e���ł͐��ȏ�ɐl�Ԃ̏X���ʂ��I�悷��B
���҂͐��ƕߗ����e���ł̑̌�����l�ԂƂ͉����A
���{�l�Ƃ͉����A�����đ哌���푈�̔s���i�s����\��ӏ��j��
�������Âɍl���A����𐔍��̎蒠�ɋL���A����ɉB����
���{�Ɏ����A��B �s����\��ӏ��̂����A���{�̕s�������A�č��̍������A
���_�I�Ɏォ�����A���ȐS�̌��@�A���ȗ͂Ȃ����ƁA
�l�Ƃ��Ă̏C�{�����Ă��Ȃ����ƁA�Ƃ�悪��œ���S��
�Ȃ����ƁA���{�����̊m���Ȃ����߁A���{�����ɕ��Ր��Ȃ�
���߁A�Ȃǂ͍����̓��{�̎p�ł���U�O�N�O�Ə�����
�ς���Ă��Ȃ��B �{���͉�c�Y���u�A�[�������e���v�Ɠ������邢�͂���ȏ��
�n�ʂ��߂�ׂ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�{���͑哌���푈����{�ɂ��A�W�A�N���ƌ���l�ɂ�
���{�ɂ��A�W�A����ƌ���l�ɂ��A�܂�����ȊO�̐l�ɂ�
���E�߂̏��ł���B
 ���{�l�̔��� ���{�l�̔���
�@�悸�́A���́A���l���L�������܊w�|���ɂƂ��čĔ̂��ꂽ���Ƃ��j�������B
�@���炭�Z�����ɂ��܂��ēǗ��ł��Ȃ��ł����u���{�͂Ȃ��s���̂��v����邱�Ƃ��ł��������̓��ɗ��l���L�̍Ĕ̂�m�邱�ƂɂȂ����A�V�[���~�肽�悤�ȋC���ł���B�R�{�����������Ģ���{�͂Ȃ��s���̂�����o�M�����߂�Ɏ��������l���L�����ɓǂނ��Ƃ��ł���������悤�Ƃ́B
�@��̑�킩�甼���I��傫���߂��A��蕔�ƂȂ�ꂽ���X�������������钆�A���l���L�͂������̐틵�̑s�₳����̔ߎS�������̂ł͂Ȃ��A��Âȕ��͂������ċɌ��ɂ�����I�悵�����{�l�̐^�����������Ɏc���Ă��ꂽ�̂��A�������̗\���Ƃ���������{������ڂ́A�����{������̓�������Ō��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̎���ɍ���x���炪���҂ł���̂���₢�������߂̋��ɂȂ��Ă���邾�낤�B
�@���{�̔s���A���{�l�̖\�͐��Ȃǂ̏������̕��͂͂Ђ��납�玄�����{�ɕ����Ă����u���{�l�͎��R�ɔ��Ȃ����������Ǝ����������v������ł�����ɂ���ĖَE����̂ł͂Ȃ�����u���I�̂��̂��܂߂ē��{�ɂ����錠�͂Ƃ������̂͑����Ă₭���I�\����ттĂ���̂ł͂Ȃ����v�Ȃǂ̋^�O���m�M�ւƓ����Ă��ꂽ�B
�@���l���L�Ĕ̂ɐs�͂��ꂽ���Z�Ɋ��ӂ����̕����I��肽���B
�@�푈�Ȃ��邱�Ƃɔ��ʂĂ����{�l�ɖ₤�A�������͖{���ɔ��Ȃ��Ă����̂��H �@
�@
|
|
![�A�}�]���̃J�[�g������](../img/viewcart.gif)




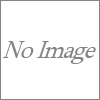

 4.5
4.5 ��_�Ɉ����ꂽ�j
��_�Ɉ����ꂽ�j ���Đ�202�@�ɋU��Ȃ��I�I
���Đ�202�@�ɋU��Ȃ��I�I ���{�C�R�q����̎���
���{�C�R�q����̎���


 �A���n�ى�{�Ȃ�Ȃ��H
�A���n�ى�{�Ȃ�Ȃ��H





